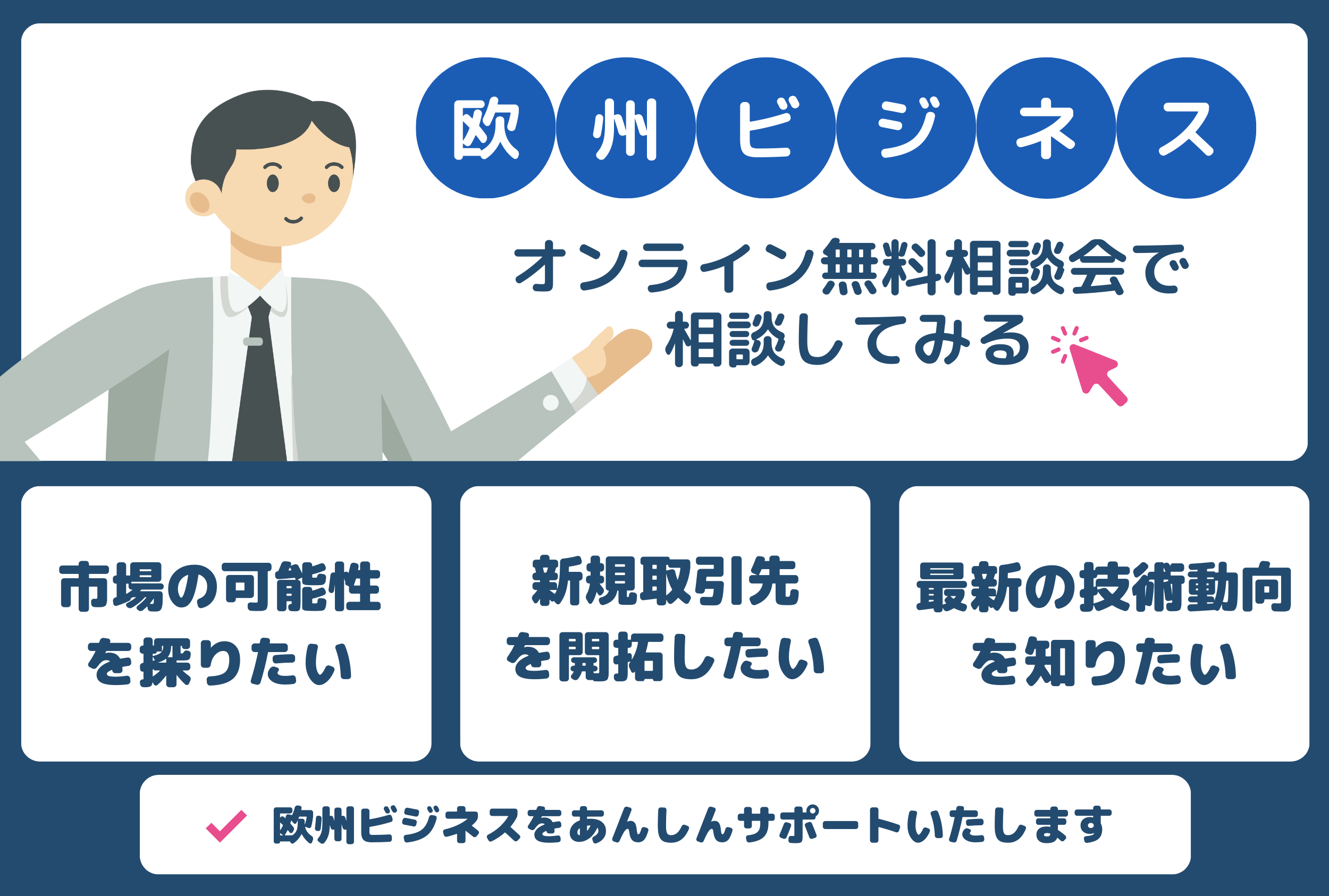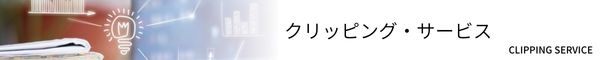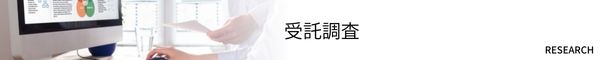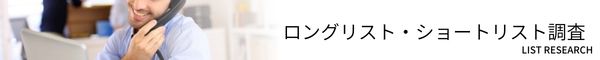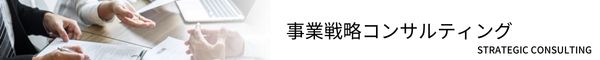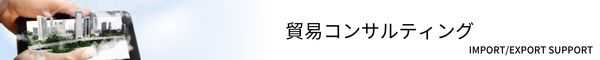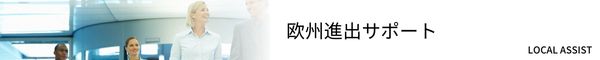欧州医薬品庁(EMA)は26日、遺伝子組み換え技術を応用して生産されるバイオ医薬品の後発品「バイオシミラー」の承認に関する指針案を公表した。バイオ医薬品のうち、抗体を主成分とする抗体医薬品について、特許期間の終了後に他の企業が先行薬に似せて製造した後発品の承認要件をまとめたもので、臨床試験の実施方法などに主眼を置いた内容になっている。EMAは来年3月31日まで意見募集を行い、各方面からの反応を踏まえて最終案をまとめる。
\免疫システムを利用してつくられる抗体医薬品は主にがんやリウマチなどの治療に使われており、副作用の少ない効果的な治療薬として注目されている。英調査会社データモニターによると、世界における抗体医薬品の市場規模は2009年の364億ドルから2015年には627億ドルに拡大するとみられているが、有力な抗体医薬品が15年まで相次いで特許切れとなるため、スイスの製薬大手ノバルティスやイスラエルのジェネリック薬大手テバなどを中心に、バイオシミラーの開発競争が激しくなっている。ただ、バイオ医薬品は化学合成の薬と比べると構造が複雑なうえ、菌やほ乳類の細胞を介して培養されるため、一般的なジェネリック医薬品のように先行品とほぼ同じ製品をつくることが極めて難しい。このため安全性と有効性の確認には新薬並みの厳格な承認手続きが必要で、臨床試験を必要としないジェネリックに比べて参入が難しい。
\EMAの指針案によると、抗体薬バイオシミラーの製造業者は先行品との類似性や後発品の有効性を証明するため、新薬と同様に臨床試験を実施しなければならない。ただし、コントロール・グループ(対象となる疾病を持たないグループ)への治験は免除される。また、バイオシミラーの承認申請に際し、当初は別の疾病に対する治療効果を証明する目的で収集したデータを、申請する案件の治験データとして提出することができる。
\欧州市場では2005年からバイオシミラーが製造・販売されているが、成長ホルモンなどと比べて格段に構造が複雑な抗体医薬品に関しては、これまでにEMAが承認したケースは1件もない。バイオ医薬品の特許切れが相次ぐ「2015年問題」を控え、抗体医薬品についても14-16年には後発品が投入される見通しだが、厳しい承認審査のため新薬とさほど変わらない開発費と手間がかかり、参入の壁は極めて高い。EMAの指針はバイオシミラーの安全性を確保しながらできるだけ開発コストを抑えることを目的としているが、開発競争に参入できるのは資金豊富な大手製薬会社や実績のあるごく一部のジェネリック医薬品メーカーに限定されるとの見方が有力だ。
\