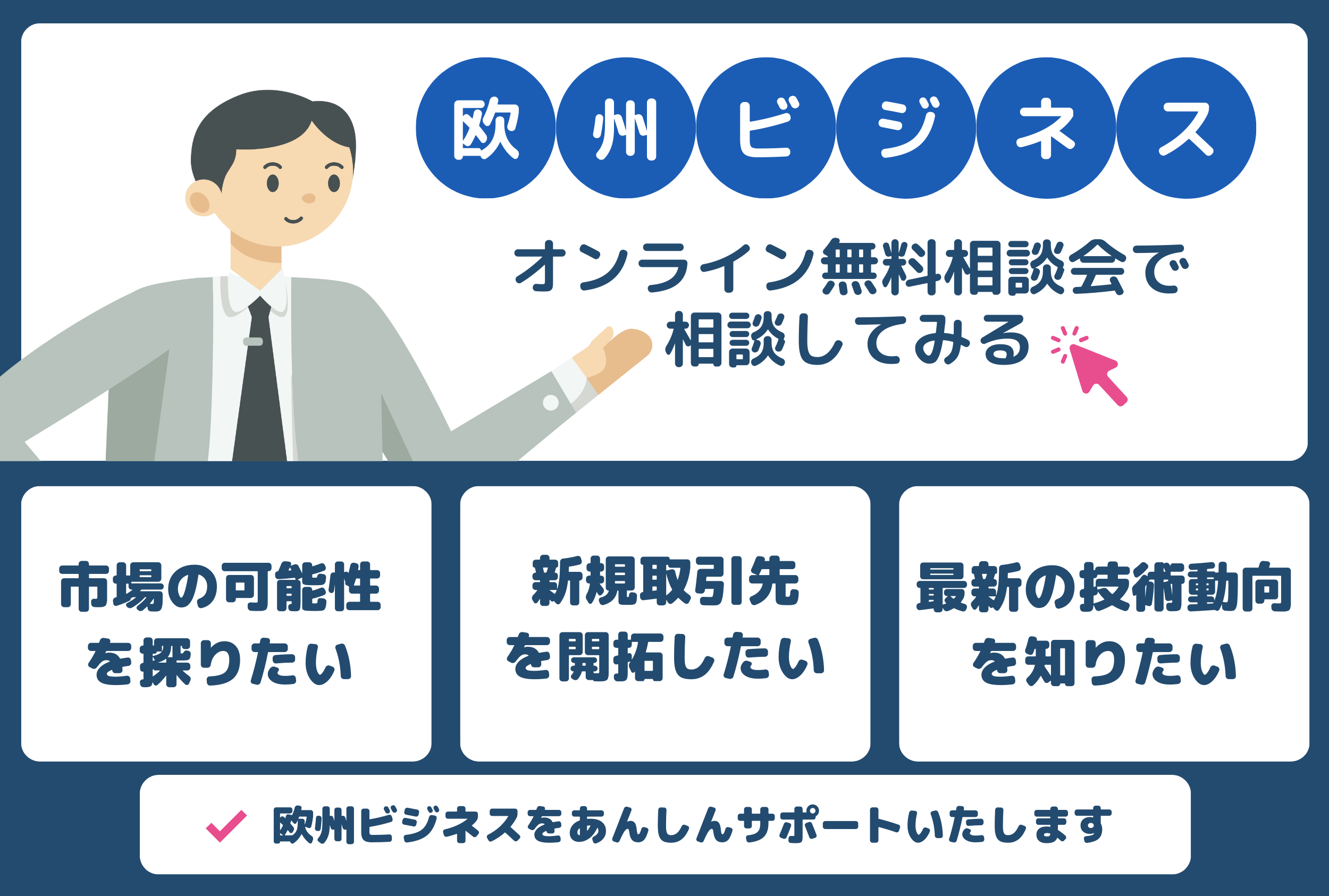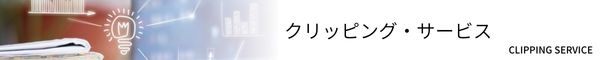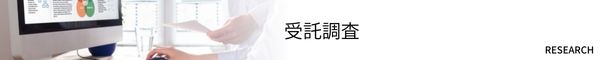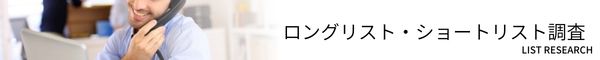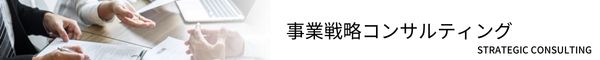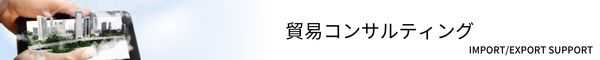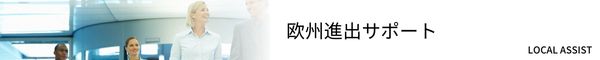欧州委員会は6日、域内の銀行を対象とする危機管理の枠組みの一環として、経営が悪化した銀行の破綻・清算処理にあたり、すべての債券保有者に損失を負担させる仕組みを導入する方針を打ち出した。先の金融危機で銀行救済に巨額の公的資金を投じた結果、多くの国で財政悪化が深刻化した反省を踏まえ、公的資金を使わずに再生の見込みのない銀行を速やかに整理・閉鎖できるようにするのが狙い。3月3日まで意見募集を行い、各方面からの反応を踏まえて2011年夏までに法案をまとめる。
\欧州委は昨年10月、金融当局に早い段階で経営不振に陥った銀行の経営に介入する権限を与えることなどを柱とする危機管理の枠組みを打ち出した。これによると危機管理は3段階で行われ、まず「準備・予防措置」として、将来的に経営難に陥った場合に迅速に対応できるよう、各銀行が再生・清算計画を策定。第2段階の「当局による早期介入」では当局が幅広い権限を持ち、問題行に対して配当の停止、経営陣の刷新、高リスク事業からの撤退、組織再編などを命じることができる。再生の見込みがない場合は事業規模にかかわらず、速やかに「清算」手続きに入り、事業売却や不良債権の分離などを進めるという手順だ。欧州委は公的資金を使わずに銀行を円滑に市場から退出させるには、最後の清算段階ですべての債権者に損失を負担させる必要があると判断した。
\欧州委はまず銀行の株式と劣後債を消却した後、普通社債の保有者に損失の負担を求める段階的アプローチを提案している。リテールおよびホールセールの預金や有担保債務などは対象外となる見通し。損失負担の手法としては債券の額面を割り引くなどが想定されているが、欧州委は適切な債務消却の仕組みを構築するため、各方面に広く意見を求めている。
\