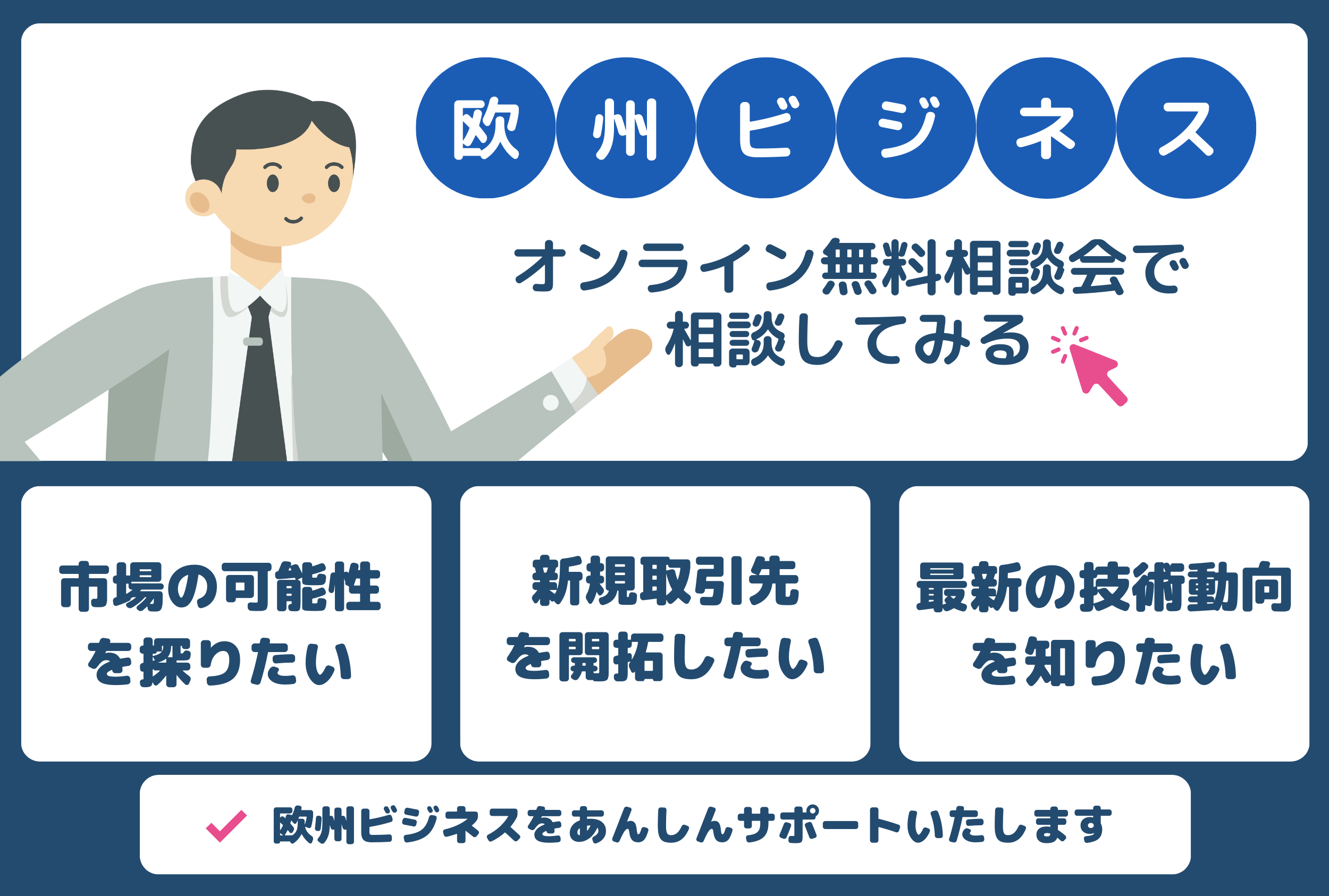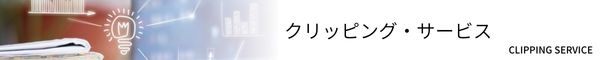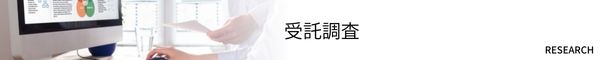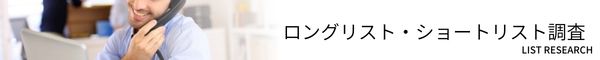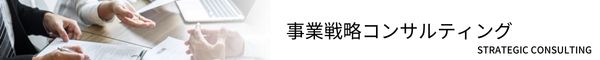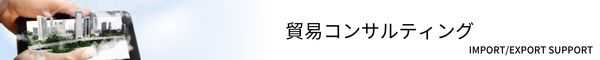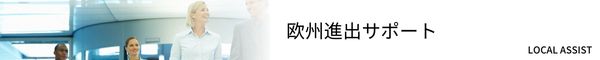欧州委員会は24日、医療機器の安全性向上を目的とする規制強化策を発表した。2010年に発覚した仏ポリ・アンプラン・プロテーズ(PIP)社のシリコン豊胸材をめぐる問題を受けた措置で、域内で販売される医療機器がEUの定める安全性や性能の基準に適合していることを示す「CEマーク」の適合性評価を行う第3者認証機関(Notified Body)が満たすべき条件や、医療機器メーカーに対する検査体制の強化などを柱とする内容。新たな規制策は加盟国との合意に基づいて、すでに多くの項目が実行に移されており、欧州委は10月にも全体の進捗状況について報告書をまとめると説明している。
\一方、欧州議会の環境・公衆衛生・食品安全委員会は25日、最もリスクの高い医療機器について、欧州医薬品庁(EMA)が指定する上位の認証機関が適合性評価を行うことなどを盛り込んだ規制案を承認した。メーカー側の自己責任を原則とした現行規制を抜本的に見直し、医療機器の承認プロセスをEUレベルで一元管理することを目指したもので、欧州委が打ち出した規制策よりさらに踏み込んだ内容になっている。10月下旬の欧州議会本会議で採決が行われる見通しだ。
\シリコン豊胸バッグ分野で当時世界3位だったPIP社が医療用ではなく、未認可の安価な工業用ジェルを用いてシリコンバッグを製造していたことが発覚した問題はPIPスキャンダルと呼ばれ、欧州を中心に大きな衝撃が走った。問題の豊胸バッグは日本を含む65カ国以上で販売されたとみられているが、体内で破裂する恐れがあることが判明しているほか、発がん性を指摘する声も出ている。
\医療機器の製造・販売にあたり、公的機関の審査を受けて国の承認を得なければならない日本や米国などと異なり、EUではメーカー自身または加盟国が指定した認証機関が所定の適合性評価を行う。安全性や性能などの基準を満たせばメーカーは「自己宣言」して製品にCEマークを表示し、域内全域で販売できる仕組みになっている。こうした制度によって欧州の医療機器メーカーは厳格な承認手続きを踏まなければならない日米などのライバルと比べ、競争上明らかに有利な立場に置かれている。このためEUでは当初、イノベーションを推進する立場から医療機器をめぐる規制の合理化が検討されていたが、PIP問題を機に安全性強化に主眼が置かれるようになり、欧州委が中心となって欧州の医療機器産業に対する信頼回復に向けた具体策を検討していた。
\欧州委が打ち出した規制強化策は、第3者認証機関を指名する際の基準や手続きなどを定めた「施行規則」と、認証機関が医療機器の安全性評価やメーカーに対する検査などを行う際の任務を定めた「勧告」から成る。これによると、加盟国は欧州委と他のEU諸国の専門家による「合同評価(joint assessment)」で適格と認められなければ認証機関を指定することができない。また、欧州委と加盟国の専門家は既存の認証機関に対して定期的に監査を実施し、自国の認証機関が適格要件を満たしていないと判断された場合、当該国は速やかに指定を取り消さなければならない。欧州委と一部の加盟国は今年に入り、試験的に11の認証機関を対象にこうした「合同監査」を実施しており、その結果、2つの機関が不適格とみなされて活動停止に追い込まれた。欧州委によると、年末までにさらに8件の合同監査が実施されるという。このほか、勧告には認証機関に対して医療機器メーカーの抜き打ち検査を実施し、製品サンプルがCEマークの適合条件を満たしているかチェックすることを義務付けることなどが盛り込まれている。
\一方、欧州議会環境委が承認した規制案は、医療機器の評価プロセスを厳格化して安全性を確保することに主眼を置いた内容になっている。具体的にはリスクが最も高い「クラスIII」の医療機器(たとえば人工心臓弁や人工股関節など)について、メーカーが自己責任でCEマークの適合性を宣言する現行システムに代わり、EMAが新たに指定する「特定認証機関(Special Notified Body)」がEU基準に基づいて製造・販売を承認する制度の導入を提案している。また、リスクレベルが中~軽度の3つのカテゴリー(「クラスIIa」「クラスIIb」「クラスI」に関しては、メーカー自身による適合性検査の結果を認証機関が詳細にチェックする仕組みが導入される。このほか糖尿病、HIV感染、遺伝子検査などに用いられる体外診断用医療機器に関する指令が改正され、倫理委員会による検証やインフォームドコンセントの徹底など、患者の保護強化を目的とした規定が盛り込まれている。
\