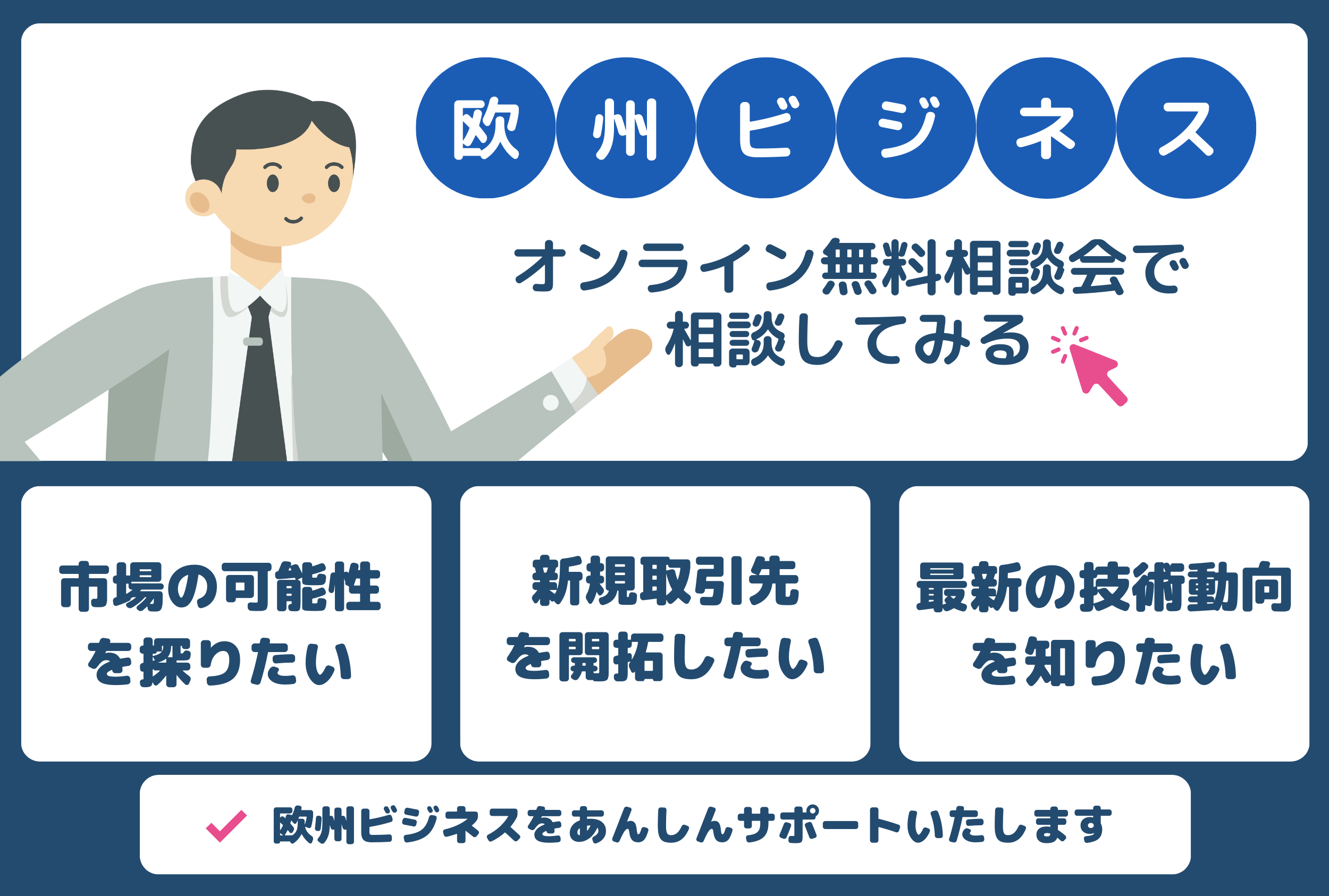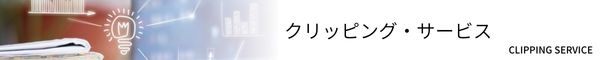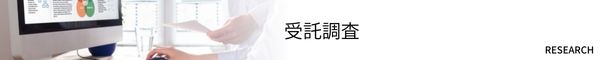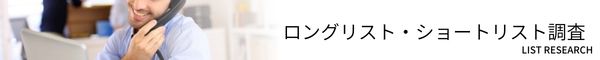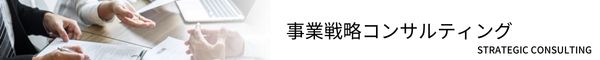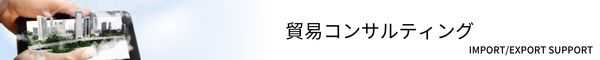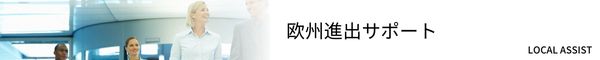東欧諸国は日本の福島原子力発電所の放射漏れ事故もかかわらず、これまでの原発政策を堅持する方針だ。ポーランド、チェコ、ハンガリーの政府、原発関係者が複数メディアに対し明らかにした。ドイツの与党3党が15日、昨秋の法改正で実現した原発の稼働延長を3カ月間、凍結することで合意したのとは対照的だ。背景には、原発を強化することで、石炭発電やロシアからの燃料への依存を減らしても電力の安定供給を維持できる体制を確立したいという事情がある。同地域でほとんど地震が起きないことも一因だ。
\ポーランド政府の広報官は15日、「国内産業が今後数十年、電力供給で問題を抱えないために、原発建設は不可欠」との見解を示した。政府は2030年までに国内発電能力の16%(6,000メガワット)を原発で賄う方針で、今年6月末までに原発の建設、運営に関する法案を成立させる計画。最初の原発(3,000メガワット)については、2016年の着工、20年の稼働を予定している。トゥスク首相は「日本の原発事故はポーランドの原発計画に影響を与えない」、「ポーランドで原発を安全運転することは技術的に可能だ」と発言。原発を建設、運転する国営電力会社ポルスカ・グルパ・エネルゲティチナ(PGE)のトーマシュ・ザドローガ社長は「事故を起こした日本の原発は旧型だ。ポーランドは最新の第3世代の原子炉を採用する」と述べた。
\チェコでは、テメリン原発(出力2,000MW)とそれより古いドゥコヴァニー原発(同1,800MW)が国内発電の約3分の1をカバーしている。政府はさらにテメリン原発で原子炉2基を増設する方針だ。同国の原子力安全局のペトル・ブランディシュ副局長は日本の原発事故に関連し、「日本からの情報が十分でない現状で、欧州の今後の原発政策を議論するのは時期尚早だ」と発言した。ただ、ダナ・ドラボヴァ局長は同国の原発計画に変更はないとしながらも、「日本が事故原発を制御できなくなった場合、欧州連合(EU)の原発政策に深刻な影響を与える」と懸念を示した。
\ハンガリーは首都ブダペストから100キロ地点にあるパクス原発で原子炉2基(総出力は最大2,000MW)増設し、2016年から稼働させる計画。既存の4基はすでに国内発電の42%をカバーしており、2基新設で原発への依存率は50%を超える。同4基はソ連型の第2世代の旧型原子炉であるため、ロシアの国営原子力関連企業アトムストロイエクスポルトが近代化することが決まっている。これにより、既存原子炉の稼働期間はこれまでより20年長い2035年まで延長された。
\ \■ トルコも原発政策の継続を表明
\ \トルコも原発政策を継続する。ユルドゥズ・エネルギー天然資源相は、「事故を起こした日本の原発は70年代初めの旧型だが、トルコは最新技術を採用する」と述べ、原発3基の建設計画に変更がないことを強調した。
\トルコ政府はまず、地中海に面する南部のメルシン県で同国初の原発を建設する計画で、昨年5月、ロシアに工事を発注した。北部シノップ県に建設する第2原発では日本の受注が有力視されている。トルコは経済成長と人口増で電力の安定供給が今後の課題となっており、2023年までに2基の原発を稼働させたい考えだ。
\ただ、トルコは日本と同じ地震国であり、第1、2原発とも地震の影響を受ける可能性がある。さらに、欧州側のテキルダーに計画されている第3原発はイスタンブール付近で今後10年以内に起こると予測されている大型地震の影響を直接受ける可能性が高く、原発反対派の強い反発が予想される。
\