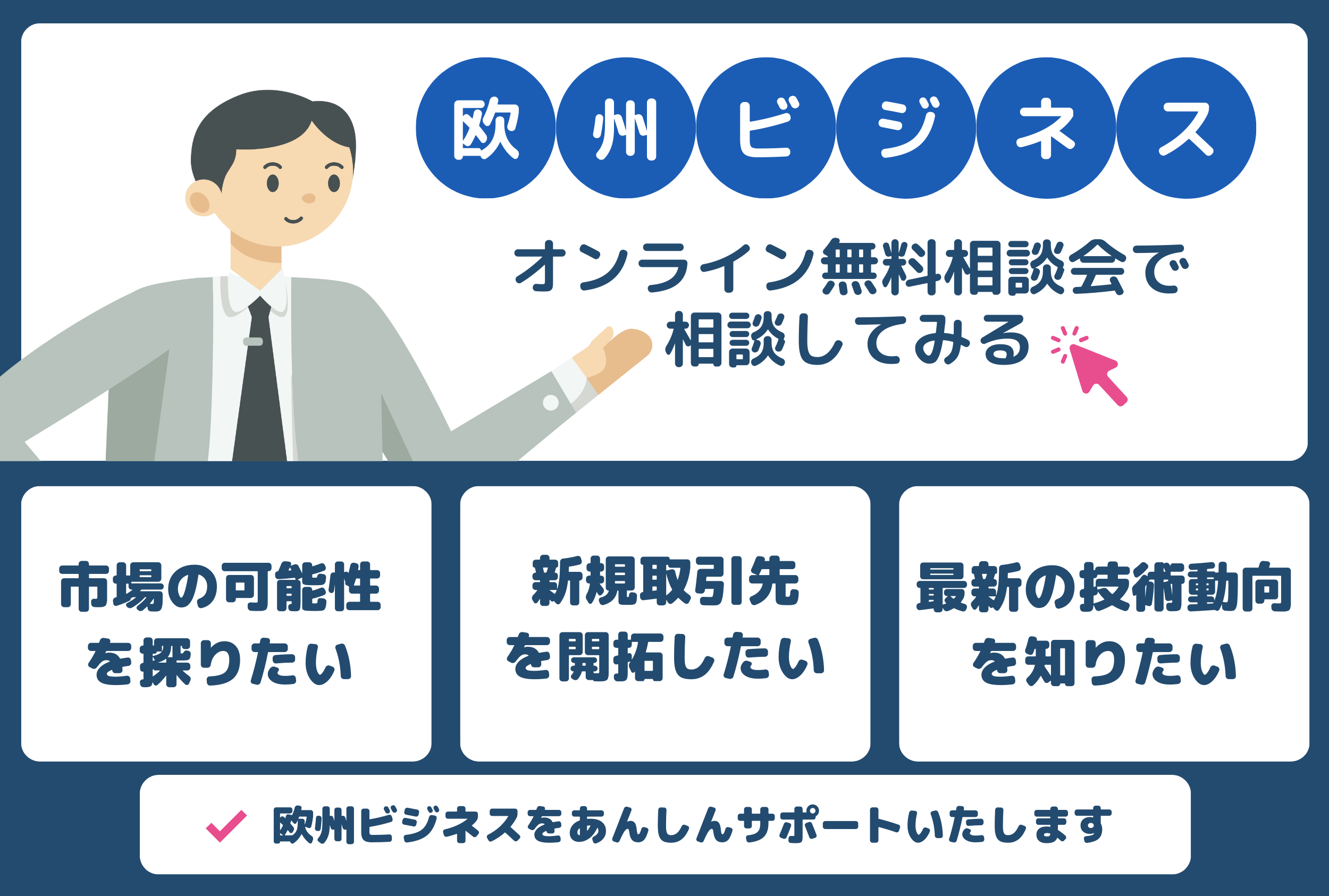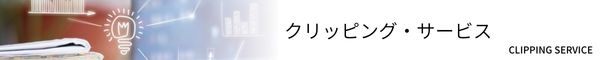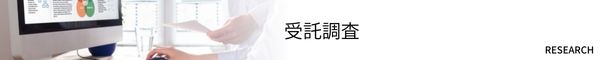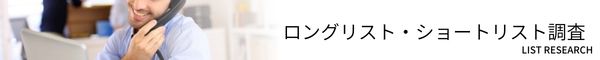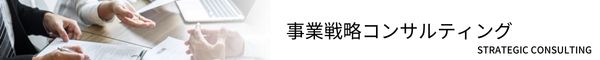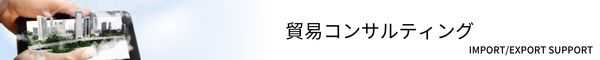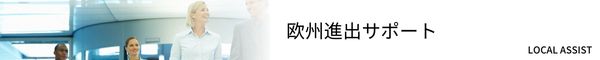ラトビアで18日、ロシア語を第2公用語に採用することの是非を問う国民投票が実施され、75%の圧倒的多数の反対で否決された。ロシア系市民の権利拡大を通じてロシアの影響が強まることを恐れるラトビア系市民の懸念が明確に示された格好だ。ラトビア系、ロシア系の政党は投票後、民族間の深い溝を埋めるため相互理解への努力を一様に呼びかけている。
\この国民投票はロシア系団体「母語」のイニシアチブで実施された。差別を感じているロシア系住民の権利拡大への願いを表わしたものだが、ソ連時代からの不信感に加わり、ロシア政府が公に運動を支援したことで、ラトビア系住民が警戒感を強めたようだ。投票率は1991年の独立以来で最高の70.5%を記録。反対票の比率も60%前後とされた事前予測を大きく上回った。
\一方で賛成票が25%を占めた事実は、人口200万人のうち約27%を占めるロシア系住民がほぼ一致して公用語化に賛成したことをうかがわせる。ただし、ラトビア語に不自由がなく、「欧州ロシア人」を自認する若い世代では投票に出向かなかった人も多かったもようだ。
\ベルズィンシュ大統領は投票結果の発表を受け、いまこそ民族間の疑念を取り払い、誤解を解き、対立を解消するための「対話」を始めるとき、と国民に呼びかけた。また、議会第1党のロシア系政党「調和センター」のウルバノヴィチュス会派代表は、公用語化の支持者はラトビア系市民やラトビア語に対抗しようとは考えておらず、両民族グループの「対話、真の協働関係、社会的統合」の実現を願っているとコメント。ただ、ロシア系住民の立場からみれば、政府が実施してきた「同化政策」は失敗に終わったとも付け加えた。
\いずれにしても、ロシア系市民の権利をめぐる問題はソ連による占領の過去と、ロシア政府の政治的思惑という現在を背負っており、細心の注意を払いながら解決していかなければならないと言えるだろう。
\ラトビアは1940年にソ連に併合され、国民の多くが当局による逮捕・強制連行、殺害という弾圧にさらされた。また、「ロシア化」政策によるロシア人の大量移住でラトビア語を話す住民の比率が急減するなど、ラトビア文化の存続が危ぶまれる事態を経験した。
\ラトビア文化の消滅を食い止めるため、政府はソ連からの独立を機にラトビア語の必修化を決定。ソ連併合後に移住したロシア系住民に対するラトビア国籍付与を見合わせるなど、「再ラトビア化」に向けた措置をとった。欧州連合(EU)などの抗議で、ラトビア語ができることを条件にロシア系住民の国籍を認めることになったが、いまでも人口の15%が無国籍のままだ。
\