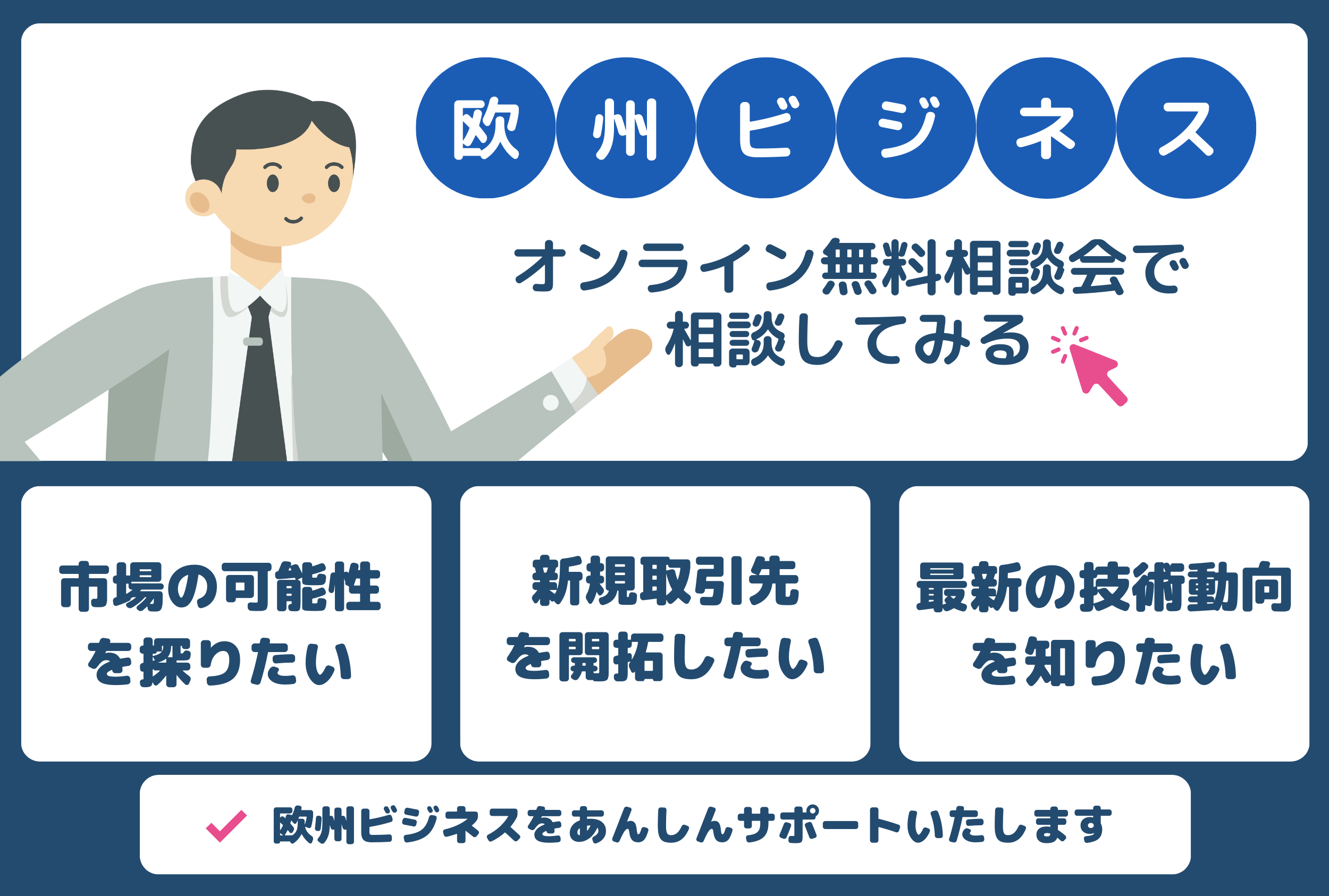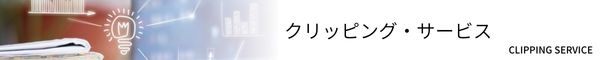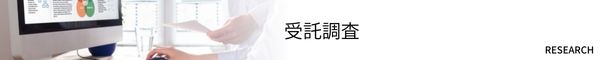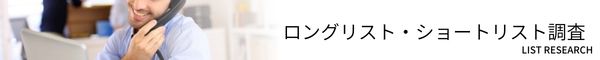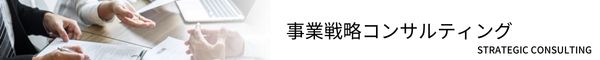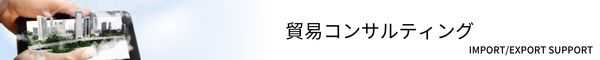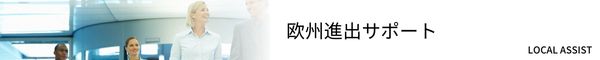2014年8月にプーチン大統領が欧州連合(EU)産食品の禁輸措置を導入したことで、ロシア人の食卓にも影響が出ている。ポーランド産のリンゴやドイツ産の食肉はベラルーシ産のもので代替できたが、困ったのはチーズだ。特に、パルメザン、カマンベール、ゴルゴンゾラ、モッツアレラなど、イタリア、フランス、ベルギー特産のチーズは、外国旅行のお土産でもなければ手に入らなくなった。
しかし、ここであきらめたらロシア人ではない。「買えないのなら作ってしまえ」――自分でチーズを作る人が出てきたのである。
オルガ・ラザレヴァさんは2年前にチーズ作りの道具や材料を販売するオンラインショップを開いた。制裁前の14年7月の売上高は5,500ユーロに過ぎなかったが、今では月11万8,000ユーロを売り上げるまでになった。
販促活動として、動画サイトに作り方を投稿している。これまでのところの人気はカマンベールとブリーチーズだという。
また、改修したオフィスの台所では、チーズを発酵させる様々な菌の特徴や、牛乳の凝固具合などを実地で教える1日講座を開催するようになった。
ロシアチーズのブリンザから、ヤギのハーブ入りフレッシュチーズ、リコッタ、モッツアレラまで様々なチーズを試食する受講生たち。「本物」の味を舌に刻んでいるようだ。
というのも、国内で「偽チーズ」の流通が大きく増えているのだ。禁輸が始まって以来、国内のチーズ生産は大きく増加した。しかし、原料となる牛乳の生産が減ったため、メーカーの多くが材料費削減に走り、植物性油脂を材料にチーズを作っている。フランスやイタリア風のチーズとしてスーパーの棚に並んでいるが、外見も味も「プラスチックのようだ」と消費者の評判は悪い。原材料表示も偽って「牛乳」となっているため、信用もガタ落ちだ。
おかげでロシア産チーズ全体の評判が落ちた。チュニジア、スイス産の輸入チーズ販売を手掛けるアレクサンドル・クルペチュコフさんは、ロシア産の「本物のチーズ」も売っているが、注文が少ないと嘆く。あまりにまずいものを食べたため、「試す気もないらしい」という。
それでもクルペチュコフさんはあきらめない。モスクワ近郊の新しいチーズメーカーが、パルメザンチーズに挑戦すると聞き、熟成後に試食するのを楽しみにしている。「制裁は当分続く。良い製品を提供していけば、その間にロシア産チーズを見直す人も増えるだろう」と楽観的だ。