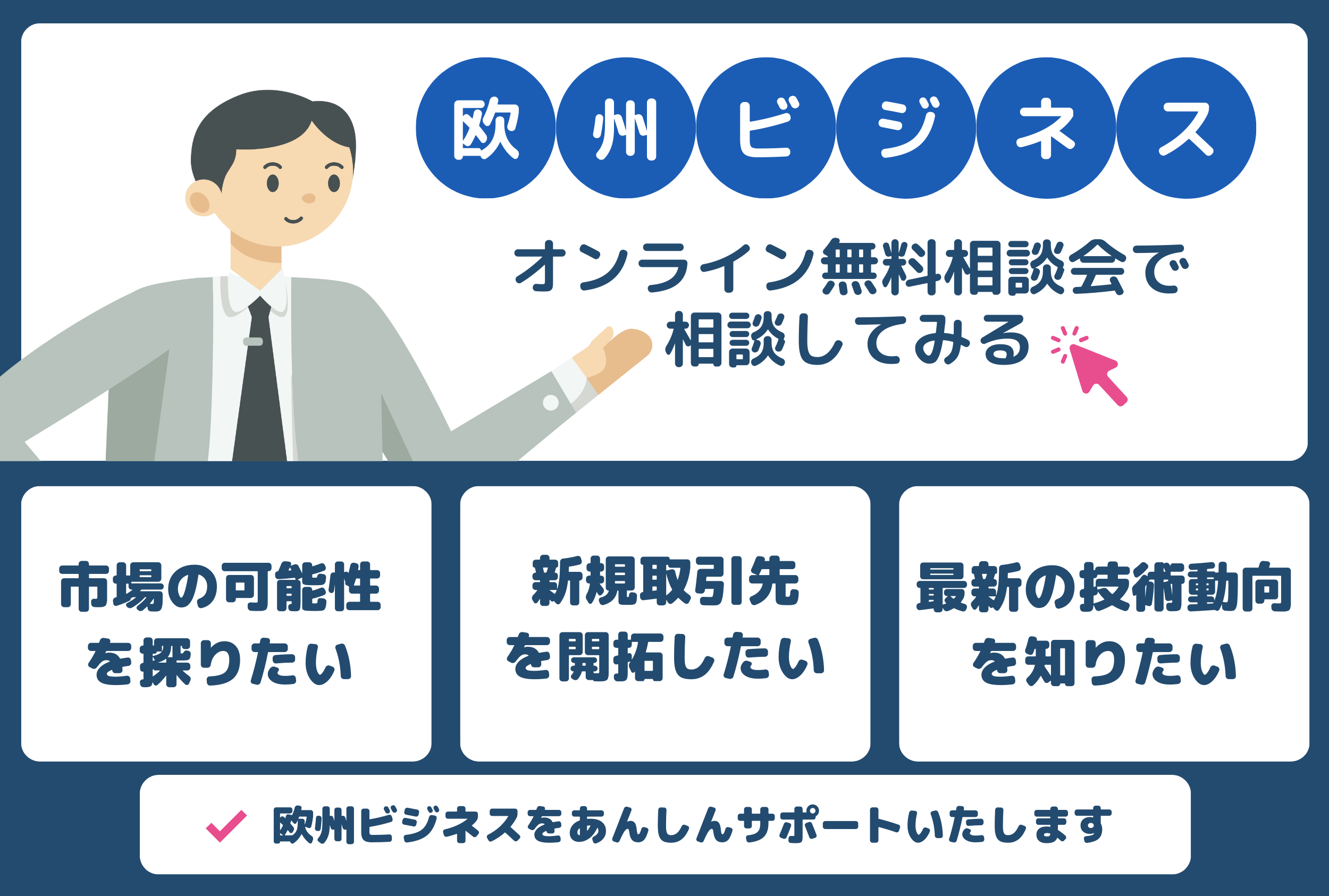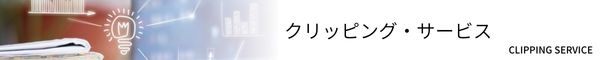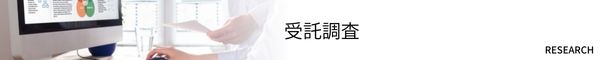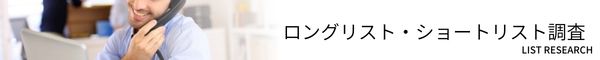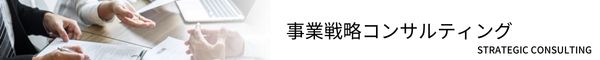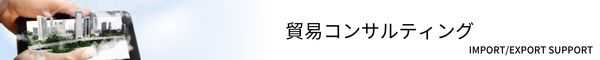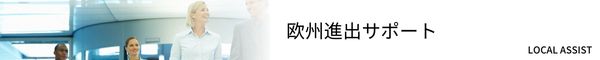ドイツの街にはネクタイ姿のビジネスマンが少ない――。この国に来たての日本人は大抵そう感じるようだ。なかには「ジーンズは国民服なのかと思った」という人もいる。
\だが、すべての人がラフな格好をしているわけではない。ドレスコードが定められている職場も少なくなく、金融都市フランクフルトでは上質な生地の背広姿が板についた銀行マンをよく見かける。
\ところで、企業は従業員の服装や外見をどこまで規制することができるのであろうか。言いかえれば、どこまでの範囲であれば従業員に対する権利の侵害にならないのであろうか。今回はこの問題をケルン州労働裁判所が12日に公表した判決文に即してお伝えする(訴訟番号:3 TaBV 15/10)。
\裁判を起こしたのはケルン・ボン空港のセキュリティチェック業務を警察から委託された企業の事業所委員会(従業員の社内代表機関)。社員の服装と外見に関する服務規定が人格権の侵害に当たるなどとして、個々の規定について司法判断を仰いだ。
\裁判官は判断に当たって、(1)業務の遂行のために各規定がどの程度必要か(2)従業員の人権がそれによりどの程度侵害されるか――という2つの観点を比較考量。人権侵害の度合いが大きければ違憲、業務上必要でかつ人権侵害の度合いが比較的小さければ合憲との結論を導き出した。
\以下、各規定についての裁判官の判断を箇条書きで説明していく。
\ \(A)下着の着用義務
\ \会社側が貸与する制服の消耗を遅らせる効果があり妥当
\ \(B)下着の色を白ないし肌色の無地のものに制限した規定
\ \人格権の侵害の度合いが小さいため合憲
\ \(C)指先からはみ出した爪の先端部分の長さを5ミリ以下に制限した規定
\ \乗客にけがをさせないために必要不可欠な義務
\ \(D)女性職員のマニキュアの色を単色に制限した規定
\ \従業員の外見を統一するという目的を達成するには制服だけで十分であり、マニキュアの制限は不要。個人の自由の侵害は容認できない。
\ \(E)男性職員の染髪の色を「ナチュラルな印象を与える色」に制限した規定と、不自然な印象を与えるカツラの使用および髪編みを男性職員に対し禁止した規定
\ \各従業員の「心身の一体性(physical integrity)」を直接的に侵害するもので違憲。また「ナチュラルな印象を与える色」といった規定そのものもあいまいなため無効。
\ \(F)男性職員に対し頭髪の清潔感を保つこと(洗髪など)を義務づけた規定と、男性に対しヒゲを完全に剃るか、整ったヒゲをはやすことを義務づけた規定
\ \乗客に面と向かって接する職業の常識で妥当
\