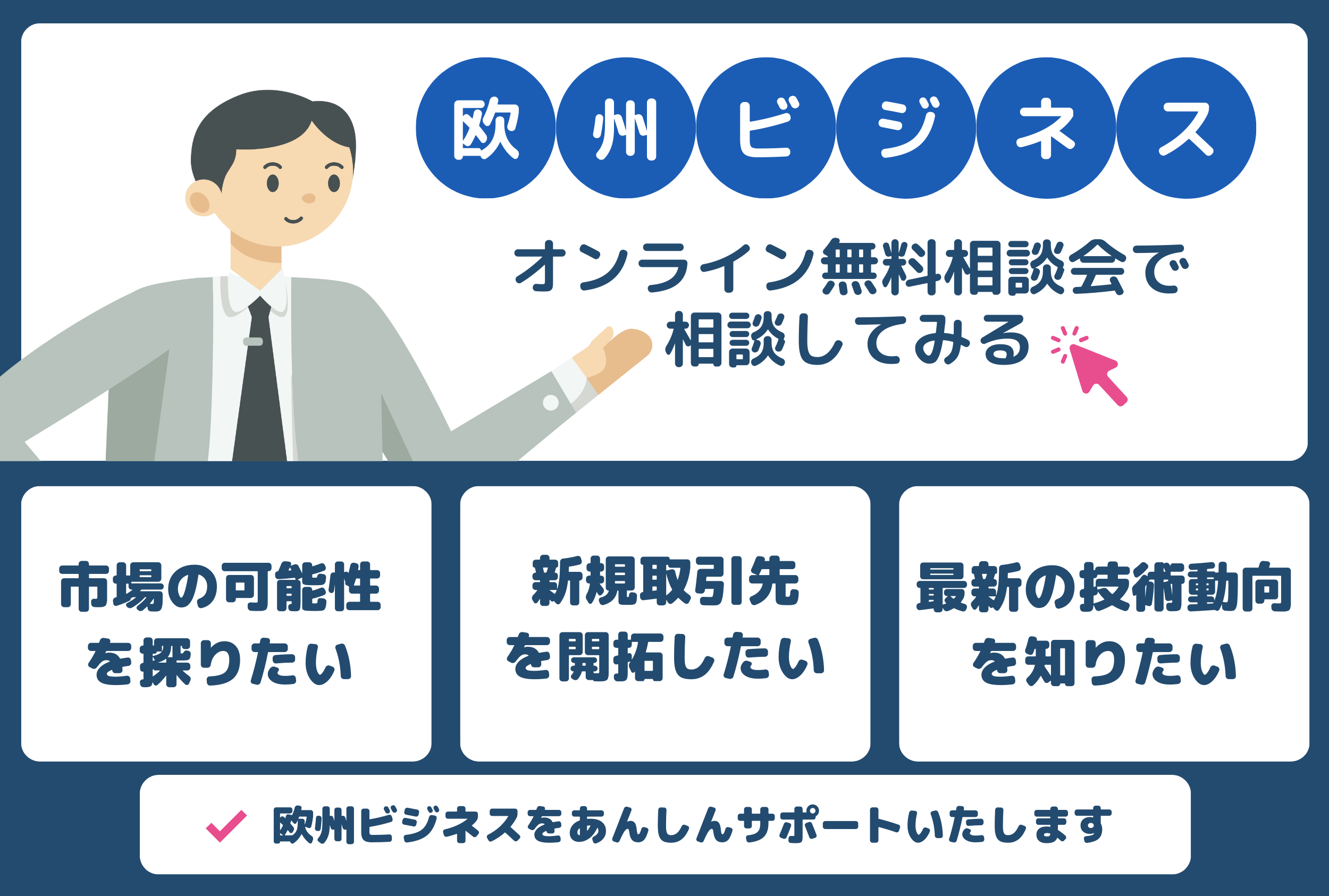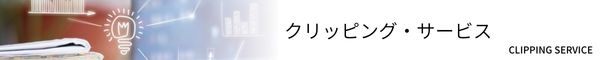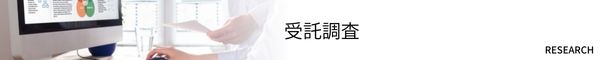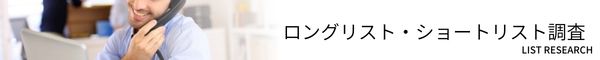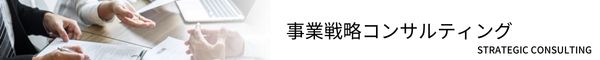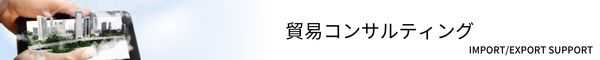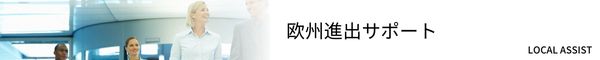ヒト胚から取り出した胚性幹細胞(ES細胞)に関する特許の是非をめぐる裁判で欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(ECJ)は18日、ヒトES細胞を利用する技術は特許保護の対象にならないとの判断を下した(訴訟番号:C-34/10)。当該の技術に特許を付与することは結果的にヒト胚の商業・産業利用を認めることになり、「人間の尊厳の尊重を損なう」と理由づけた。
\係争となっていたのはボン大学のオリバー・ブリュストレ教授が中心となって開発した、ES細胞を神経前駆細胞に培養する技術およびこれを脳・神経疾患患者に移植する技術に関する特許で、ES細胞を得るために胚盤胞と呼ばれる、受精から約5日目の胚を利用する。これに対し、環境団体のグリーンピースが「ヒト胚を金儲けの道具にすることは生命の尊厳を冒す」として提訴していた。ドイツの連邦特許裁判所は、ヒト胚の利用に関する部分の特許無効を言い渡したが、ブリュストレ教授が判決を不服として上告。連邦司法裁判所(最高裁)は、バイオテクノロジー発明の法的保護に関するEU指令(98/44/EC)でヒト胚の定義(卵細胞はいつから胚と呼ばれるか)がなされていないなどとして審理を中断し、ECJの判断を仰いでいた。
\ECJの裁判官は、EU指令からは“人間の尊厳”を損ない得る発明への特許付与をあらゆる形で排除する意図が読み取れると前置きしたうえで、卵細胞は受精の瞬間からヒト胚になるとの解釈を示した。ブリュストレ教授の発明が胚盤胞を使用することについてはドイツの裁判所が判断すべき内容として、詳しく言及していない。
\ヒト胚の商業・産業利用を目的とする発明を特許保護の対象外とする規定が学術研究目的にも適用されるかという争点については、「学術研究の結果が特許(商業利用)のベースであり、両者を分けることはできない」と明言し、研究目的でも特許の対象にならないとの判断を示した。ただ、ヒト胚をヒト胚の治療・診断目的で使用する(着床前診断などの)場合については、特許付与(商業利用)は認められるとした。
\