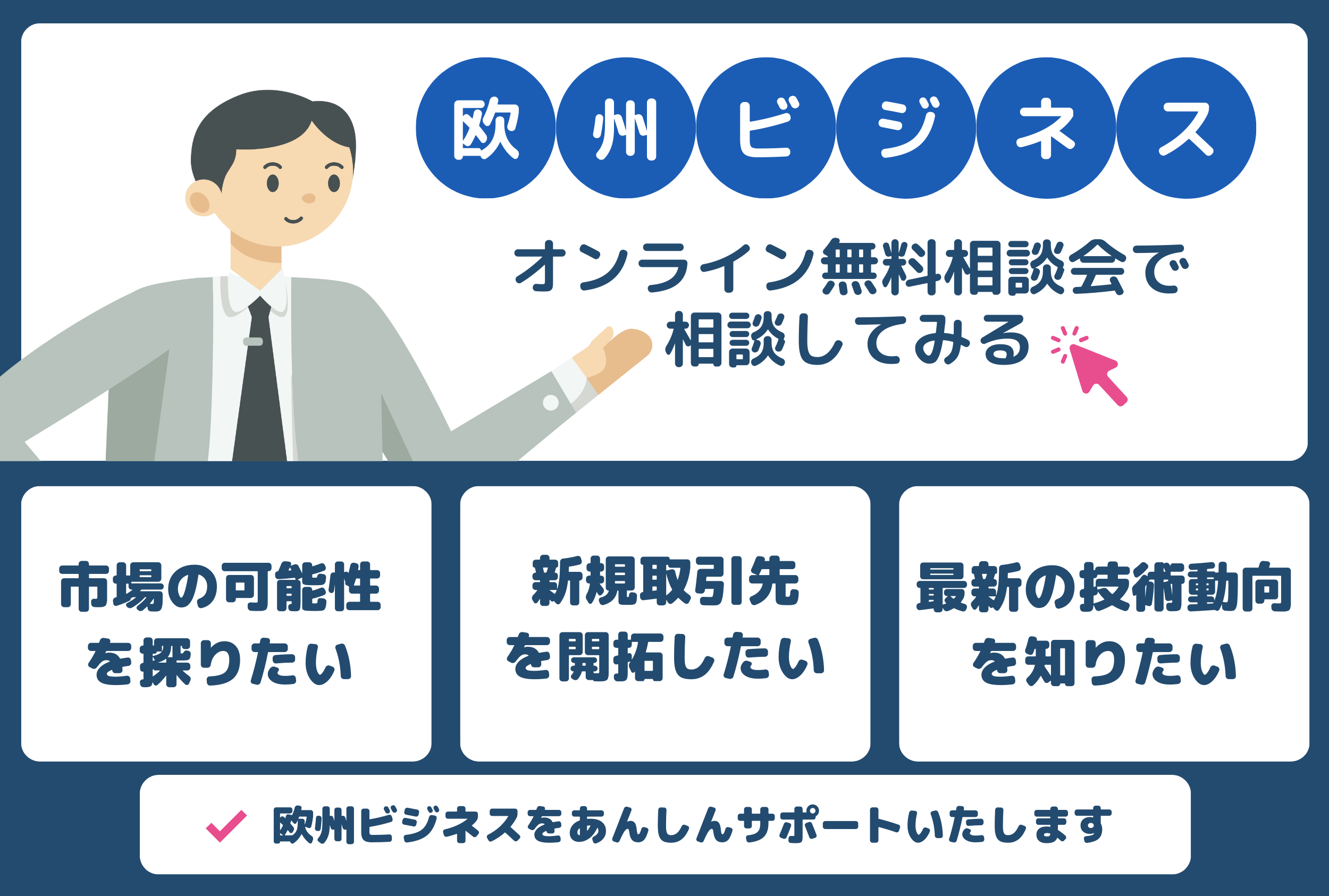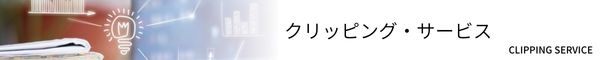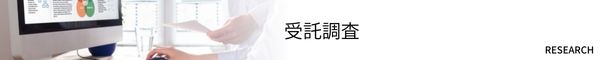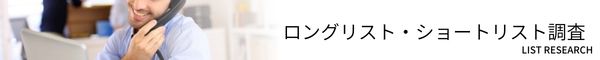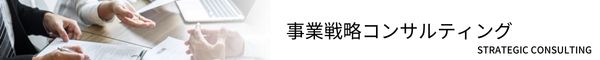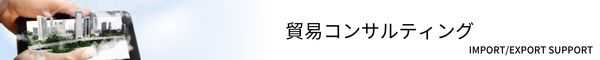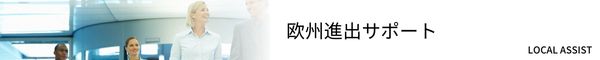過分極化したキセノン(129Xe)とバイオセンサーを用いた核スピン共鳴断層撮影(MRT)で標的分子(や細胞)の有無を短時間で正確に診断する手法を、ベルリン分子薬理学研究所(FMP)のチームが開発した。キセノンガスを吸入投与後、キセノンを捕えるケージ構造を持つバイオセンサーを接種、キセノン原子の信号をとらえて標的分子を検出する。画像再構成システムを最適化することで2分以内の診断が可能という。
\コンピューター断層撮影には大きく分けてMRTとポジトロン断層法(PET)がある。MRTは生体中の水素原子の核磁気共鳴現象を利用するもので、臓器や生体組織の形態を観察できる。ただ、水素原子は体内にふんだんに存在するものの磁場が弱いため、空間が多い肺細胞などの検査は困難だ。また、細胞の種類や代謝レベルなど生体機能上の情報はほとんど得られない難点がある。一方、PETは放射性元素の同位体を利用して生体機能の観察ができるものの、3次元解像能がやや低いうえ、放射線被ばくが避けられない欠点がある。
\FMPの研究チームはこうした事情を踏まえ、MRTとPETの長所を併せ持つ新たな手法の開発に取り組んだ。チームが着目したのは過分極した129Xeだ。同物質は水素原子に比べMRTの感度を数千~数万倍に引き上げられるため、従来の手法では検査が困難だった領域でも鮮明な画像が得られる。また、水や血液への溶解度が高く、人体に無害なため臨床に応用しやすいメリットがある。
\チームはキセノンを画像の鮮明化だけでなく、生体機能の観察でも活かせる方法として、キセノンを取り込むバイオマーカーと組み合わせるというアイデアにたどり着いた。試行錯誤の末、ケージ様超分子化合物であるクリプトファンをもつバイオマーカーを開発した。分子構造を工夫し、標的分子と結び付いたバイオマーカーがキセノンをケージに取り込むと磁気信号が打ち消されるようにするとともに、ケージがキセノンをとらえても数ミリ秒後に離す(可逆的結合)ように制御。キセノンの結合・分離で磁気が点滅するように変化する場所をとらえることでターゲット分子を検出できる仕組みだ。
\研究成果は『Angewandte Chemie』に掲載された。
\