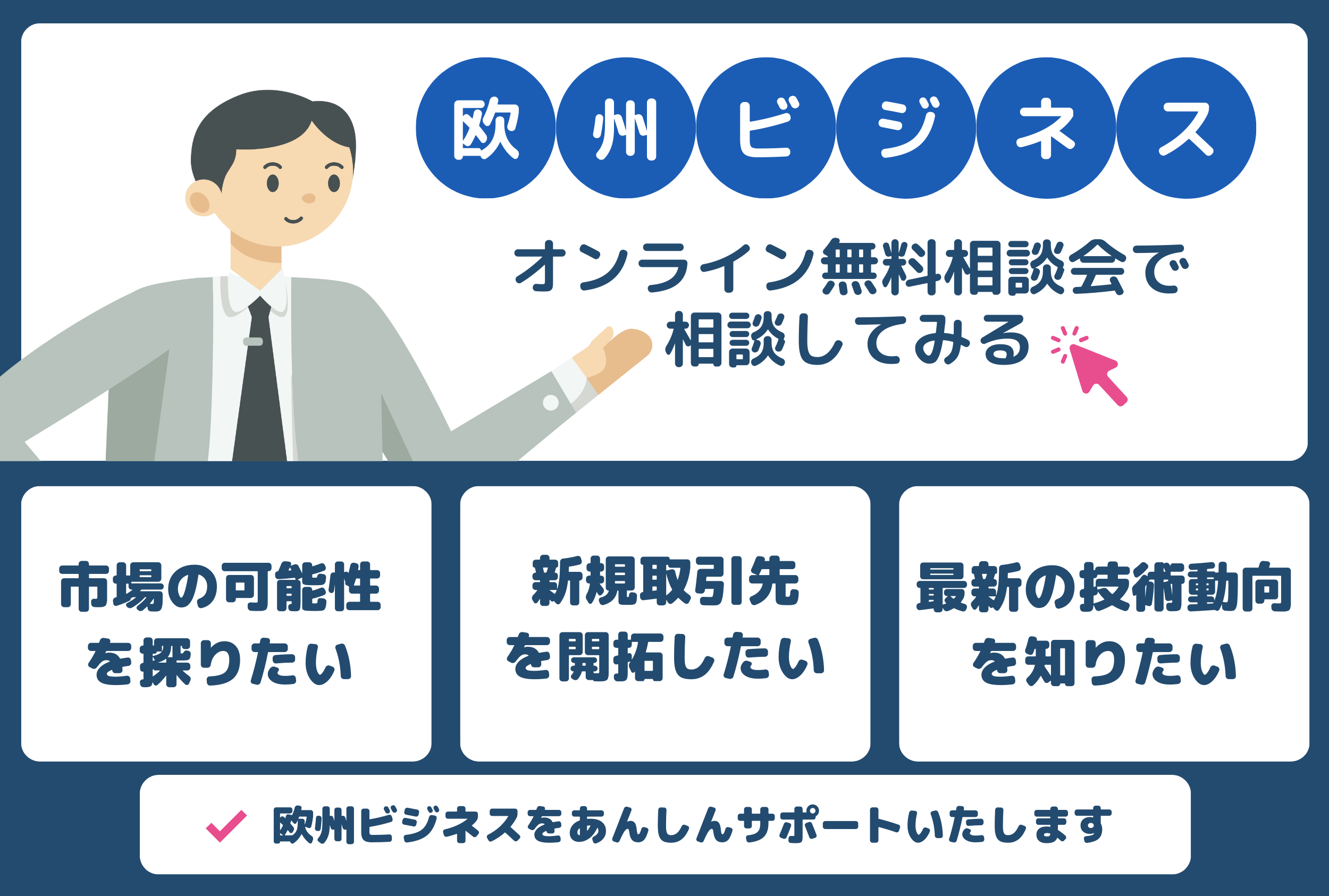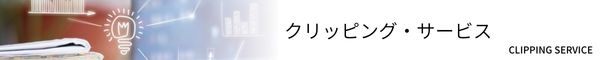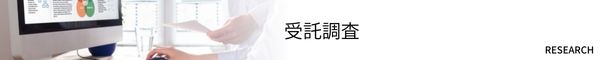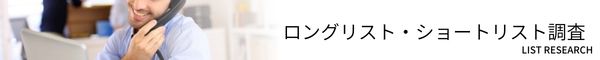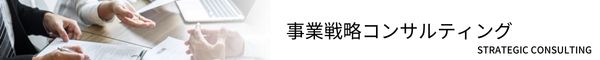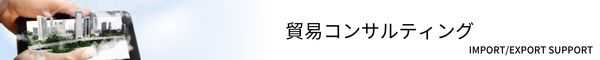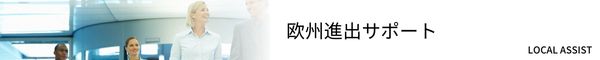ドイツには転勤を嫌がる人が多いため、異動命令は係争の原因になりやすい。家族や友人関係、子供の生活環境を維持したいと強く思う人が多く、サラリーマンは転勤が当たり前という日本の常識は必ずしも通用しない。これは企業の側からすると、転勤がありうることを労働契約に明記しておく必要があることを意味する。
\この労働契約に記された勤務地規定の是非をめぐる裁判で、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は6月に判決(訴訟番号:10 AZR 296/11)を下した。このほど判決文が公表されたので、取り上げてみる。
\裁判を起こしたのは被告の航空会社にパーサー(客室乗務員のリーダー)として勤務する女性。同パーサーはまず、1990年に被告企業の子会社(S社)に採用され、後に被告企業に移籍した。労働契約には「勤務地は原則としてフランクフルト・アム・マインとする。(雇用主は原告を)一時的あるいは長期間、他の勤務地に投入できる」と記されている。
\原告は1995年11月1日付でハノーバー空港勤務となったが、被告は同空港発着便の利用者減少を受けて、2009年12月末で同拠点を閉鎖することを同年7月に決定した。その際、引き続きハノーバーで勤務したい職員に対しては、子会社Bの一般の客室乗務員として雇用することを提案。原告はこれに対し、B社でのハノーファー勤務を希望するが、あくまでパーサーとしてだとの意向を伝えた。
\被告はこれを受け、フランクフルトにパーサーとして異動することを原告に命令。原告は労働契約の勤務地規定はあいまいだとして、定義が不明確で理解不能な契約規定を無効とした民法典(BGB)307条1項の規定を根拠に、同勤務地規定と異動命令の無効確認を求める裁判を起こした。その際、ハノーバー勤務が14年と長期に及んだことを根拠に、同地で勤務を続ける権利が発生したと主張した。
\第2審のニーダーザクセン州労働裁判所は原告の訴えを認める判決を下した。これに対し連邦労裁は、労働契約などに特別な取り決めがない限り雇用主は被用者の勤務地などを決定できるとした営業令(GewO)106条の規定を指摘したうえで、異動命令が民法典315条3項に定める「公正な裁量(billiges Ermessen)」に従って下されたていれば命令は妥当だとの判断を提示。下級審では異動命令が公正な裁量に基づくものかが審理されていないとして、ニーダーザクセン州労裁に裁判を差し戻した。差し戻し審では原告の扶養義務や生活環境などあらゆる事情を斟酌したうえで判決を下すよう指示している。
\一方、ハノーバー勤務の既得権が発生したとする原告の主張については、勤務期間が長期化してもそのような権利は生じないとの判断を示した。
\