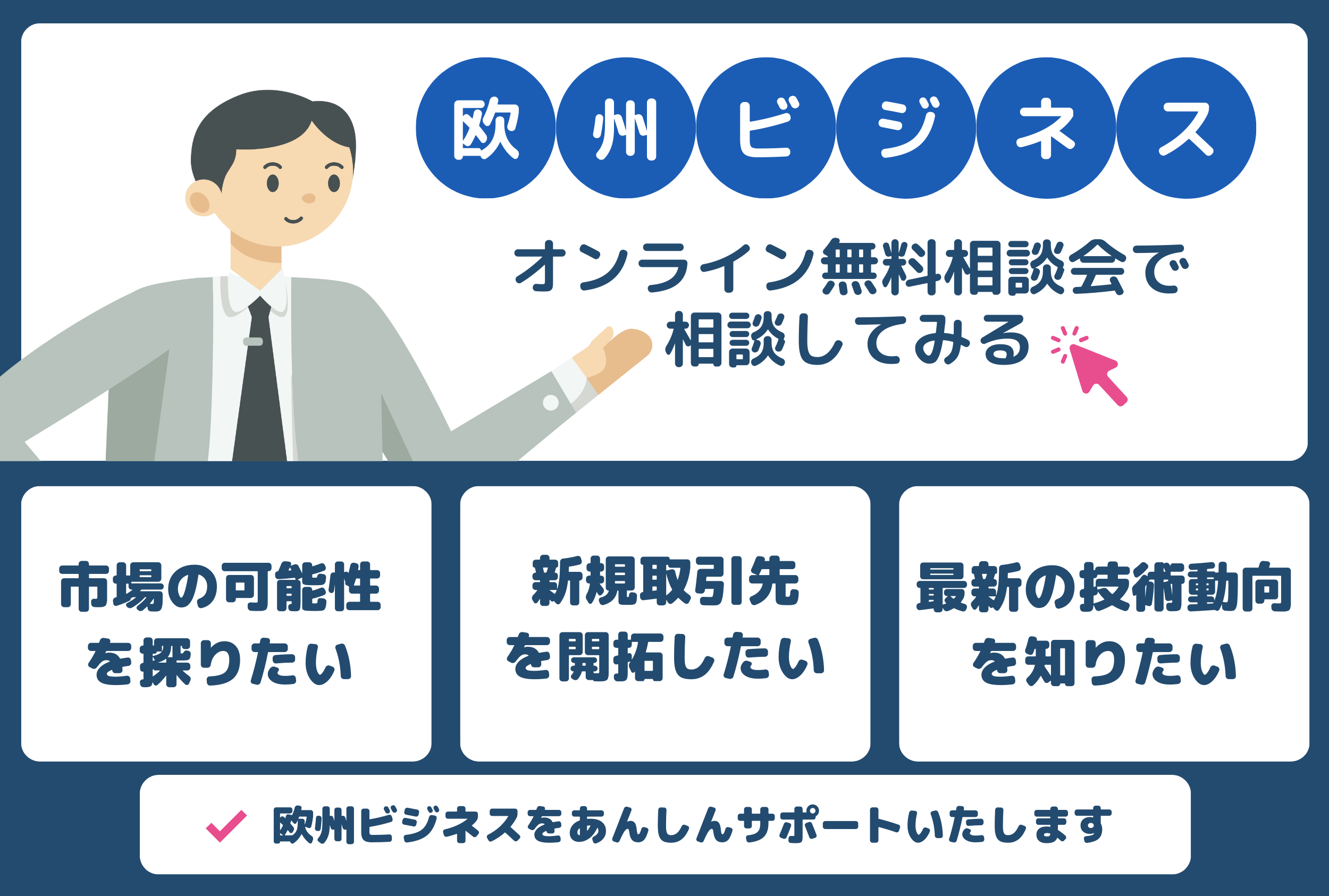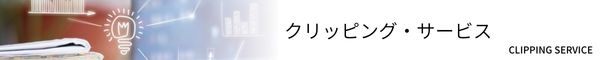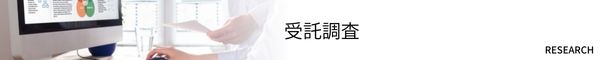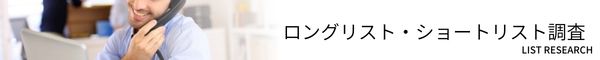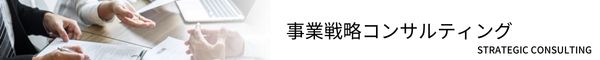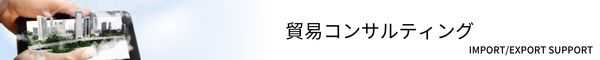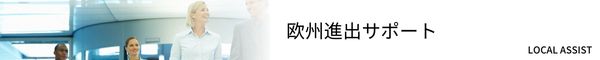ヒト胚から取り出した胚性幹細胞(ES細胞)に関する特許の是非をめぐる裁判で独連邦司法裁判所(BGH、最高裁)は11月27日、ヒト胚を破壊せず(死なさず)にES細胞を得ることができる限りにおいて特許付与は可能との判断を示した。また、ES細胞は受精卵と異なり単独では個体をつくり出すことができず、法的にみてヒト胚には当たらないと言い渡した(訴訟番号:X ZR 58/07)。
\係争となっていたのはボン大学のオリバー・ブリュストレ教授が中心となって開発した、ES細胞を神経前駆細胞に培養する技術およびこれを脳・神経疾患患者に移植する技術に関する特許。ES細胞を得るために胚盤胞と呼ばれる、受精後およそ5日目の胚を利用する。これに対し、環境団体グリーンピースはヒト胚の「搾取」につながるとして、独連邦特許裁判所に特許無効を申し立て、2006年に特許の一部無効が言い渡された。同教授はこれを不服としてBGHに上告。同裁は09年、欧州司法裁(ECJ)の判断を仰いだ。
\ECJは11年、欧州特許条約及びバイオテクノロジー発明の法的保護に関するEU指令(98/44 EC)の主旨からみて、人間の尊厳を損ないうる発明への特許付与は容認されないと指摘。ヒト胚をヒト胚の治療・診断目的で使用する(着床前診断などの)場合については、特許付与(商業利用)は認められるとしながらも、「胚盤胞期のヒト胚から幹細胞を取り出す行為はヒト胚の破壊を伴っている」として、特許適格性を欠くとの判断を示したうえでBGHに審理続行を求めた。
\ブリュストレ教授はECJの判断を受け、同教授の手法は「胚を破壊していない」として特許の一部有効を求める予備的請求を行い、今回の判決ではこの主張が認められた格好だ。
\