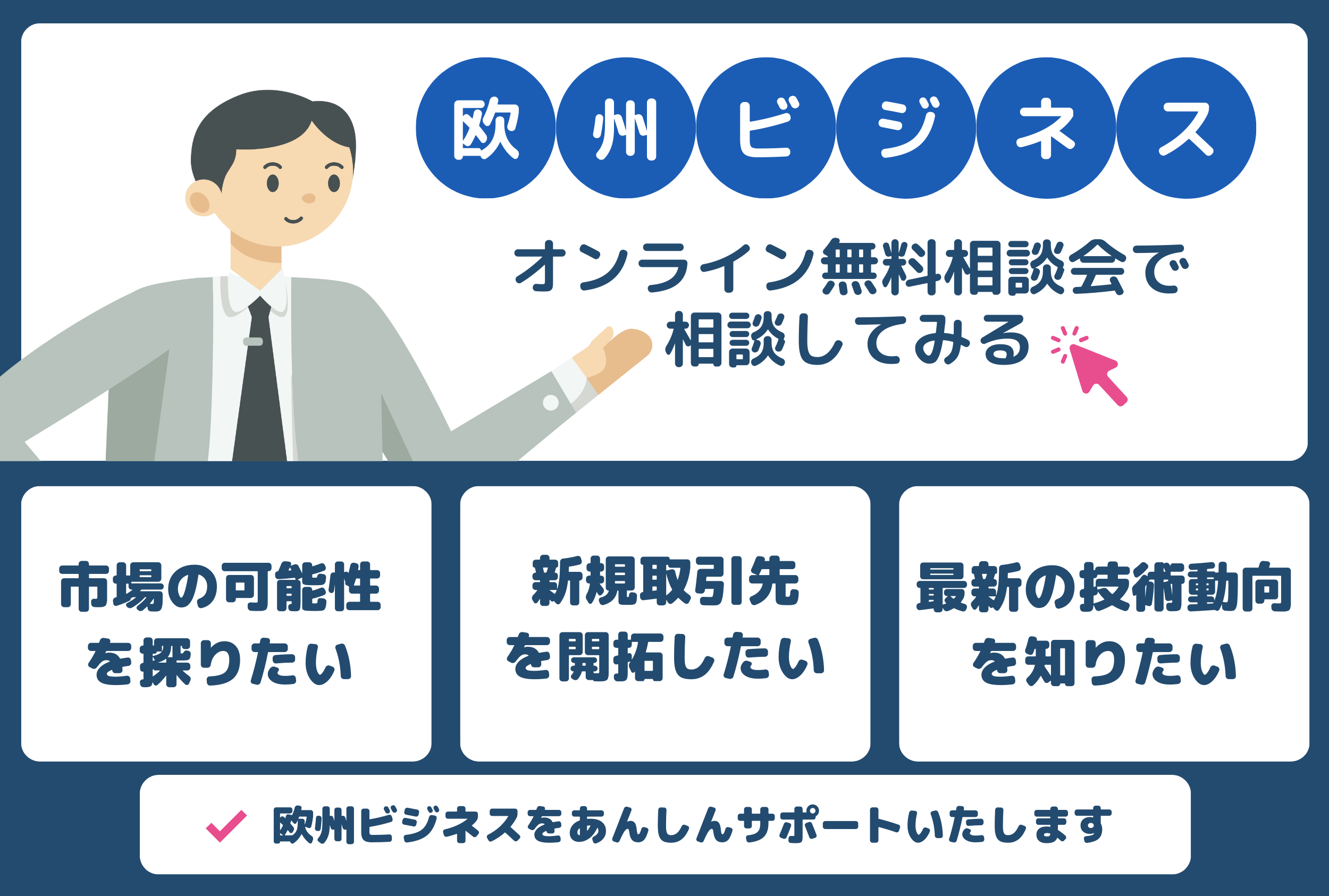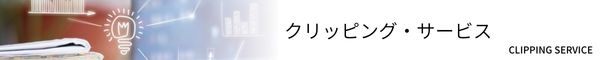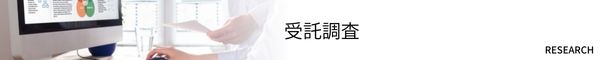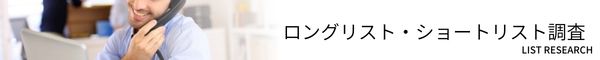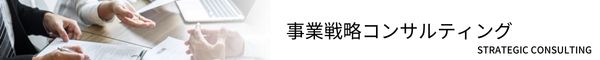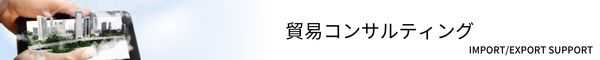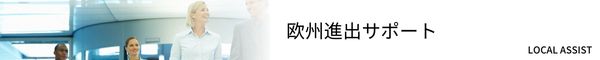連邦政府は22日の閣議で、ガブリエル経済相が作成した再生可能エネルギー法(EEG)の改正に向けた基本方針を承認した。再可エネ向け助成金総額の急増を受けて消費者や企業の負担が膨らんでいることに対応したもので、助成コストの上昇抑制と、エネルギー集約型企業に認める助成分担金(Umlage)負担軽減措置の見直しの2つの柱からなる。政府は今後、各方面の意見を踏まえたうえで法案を作成し、4月9日に閣議決定。連邦議会(下院)と連邦参議院(上院)の承認を経て8月1日付で施行する計画だ。
\ドイツは再生可能エネルギーの普及を後押しするため、従来型電力に比べて発電コストが高い再可エネ電力が助成金を受けられるようにしており、再可エネ発電で生産された電力を市場価格よりも高額の固定価格で買い取ることが送電事業者に義務づけられている。買い取り価格と市場価格の価格差が助成金に当たり、最終的に電力料金に上乗せされて、消費者や企業などの需要家が負担している。
\再可エネ発電事業者は助成金を20年間にわたって受け取れることから、投資リスクが低い。このため、国内の総発電量に占める再可エネ発電の割合は同助成制度が始まった2000年の6.6%から13年には23.4%へと急速に拡大。助成金総額は現在、年204億ユーロに達している。
\これに伴い消費者や企業が負担する助成分担金の額は急増しており、昨年は前年比47%増の1キロワット時(kWh)当たり5.277セントに上昇。今年も18%増えて、同6.24ユーロに達した。
\ \自家発電も助成金負担の対象に
\ \現状を放置すると助成分担金は雪だるま式に膨らみ、消費者と企業が負担しきれなくなることから政府はEEG法の改正に乗り出した。
\同法の改正方針ではまず、国内の電力供給全体に占める再可エネの割合を25年までに40~45%、35年までに同55~60%に拡大するとの数値目標を設定。そのうえで、電力の安定供給を維持しながら妥当なコストで同目標を実現するための方策が記されている。
\具体的には(1)助成対象をコストの低い技術に集約する(2)1kWh当りの助成額も引き下げていく(3)再可エネ発電の種類ごとに国全体の新設容量の規模を調整し、助成総額が無秩序に膨らまないようにする(4)再可エネ発電事業者に電力を自らの責任で販売することを義務づける(5)助成額を入札で決定する制度を導入する(6)助成負担金の軽減ルールを見直す――などが盛り込まれている。(1)~(5)の措置により1kWh当たりの助成額を2000~14年の平均17セントから同12セントに引き下げる考えだ。これらのルールが適用されるのは新規の施設のみで、既存施設にはこれまで保証してきた助成金を支払い続ける。
\助成対象とする再可エネ発電の種類としては陸上風力発電、洋上風力発電、太陽光発電、バイオマス発電を挙げている。ただ、バイオマス発電については助成対象を廃棄物系のものに制限し、農作物由来のものは除外する。
\(3)に関しては、陸上風力発電と太陽光発電の国内新設能力をそれぞれ年2,500メガワット(MW)とする考え。これを超える分については助成額を大幅に引き下げて新設能力が目標値を大きく上回らないようにする。バイオマス発電では新設能力を年100MWに設定している。
\一方、洋上風力発電の新設能力は2020年までを計6.5ギガワット(GW)とし、従来計画の10GWから縮小した。背景には、洋上風力発電パークの設置は技術的に難しく、20年までに新設能力で10GWを確保することは実施的に不可能という問題がある。
\再可エネ電力を発電事業者の責任で売却するルールは8月1日付で導入する考え。対象となるのは発電容量500キロワット(kW)以上の新規設備で、16年1月には同基準が250kW以上に引き下げられる。17年1月からは100kW以上が同義務の対象となる。この措置により発電事業者は電力需要と価格が高いときに売電するようになるため、助成額の低下につながる。
\(5)は再可エネ電力の入札で最低価格を提示した発電事業者が落札するというルールで、再可エネの助成制度に競争原理を導入することになる。政府はまず17年から地上設置型ソーラー発電施設を対象に試験導入。その結果を分析したうえで、全面導入に踏み切る意向だ。
\助成金負担の軽減ルールは本来、厳しい国際競争にさらされるエネルギー集約型企業を念頭に導入された。だが、負担軽減を受けるのに必要な基準が2012年に緩和された結果、内需型企業も助成を受けられるようになり、軽減対象となる企業の数は急増。昨年は1,700社、今年は2,700社以上へと拡大した。
\そのしわ寄せで同措置の恩恵を受けない企業と消費者の負担は大きく増加している。同ルールに対しては欧州連合(EU)の欧州委員会がEU競争法違反の疑いで審査を開始したこともあり、政府はルール改正に踏み切る。
\政府はこのほか、これまで助成金負担の対象外としてきた自家発電についても負担義務を課す意向だ。連邦経済省が公表した改正方針には新設発電施設のみを対象とすると記されているが、メディア報道によると、非公開文書には既存施設も対象に加える方針が盛り込まれているといい、経済界に波紋が広がっている。
\