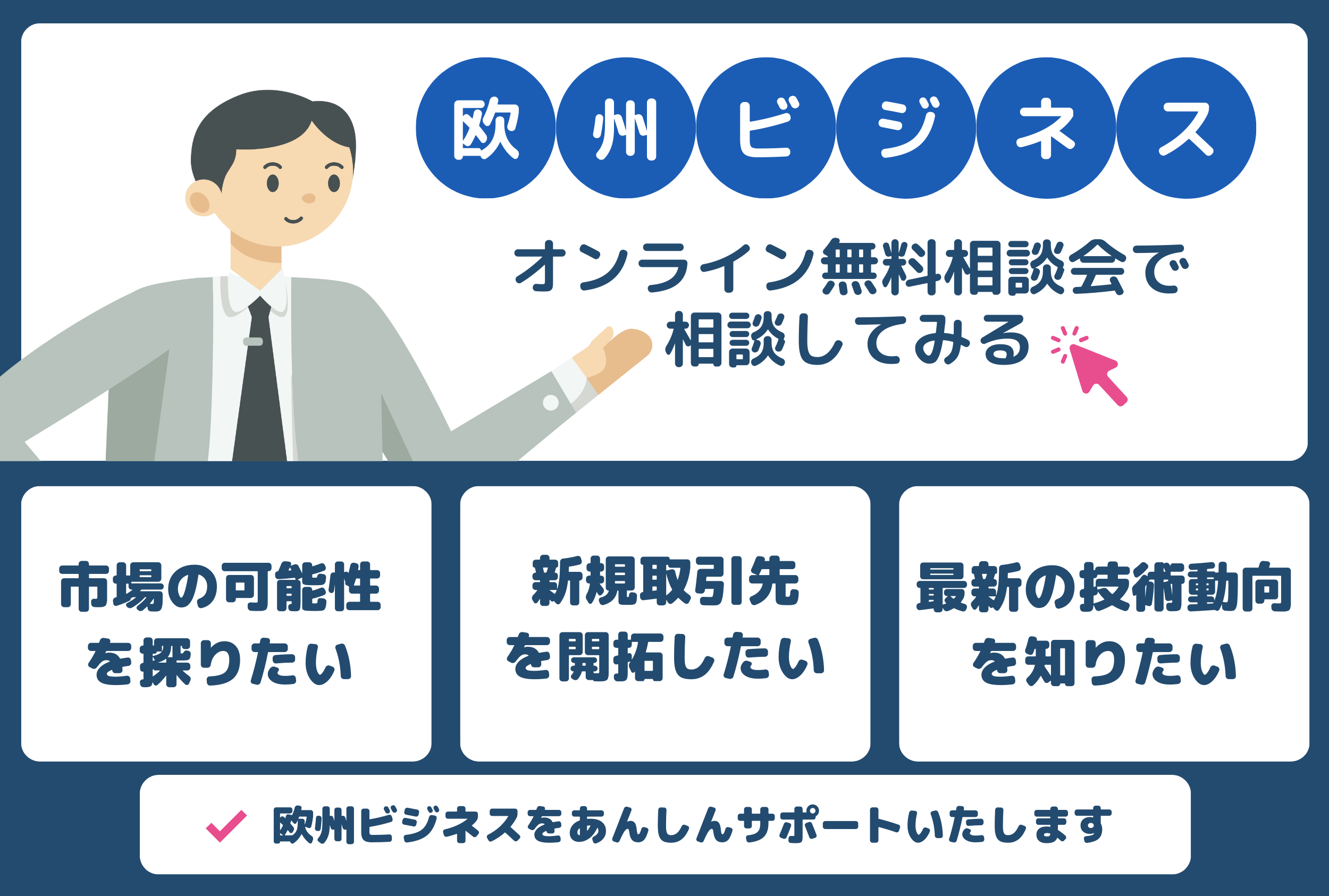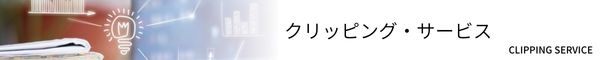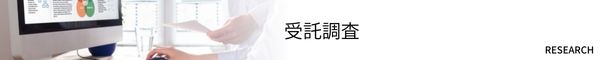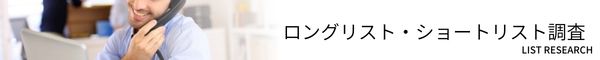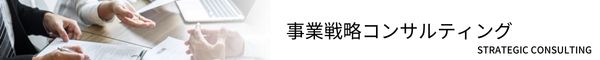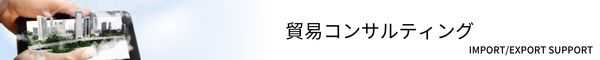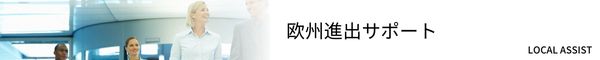ドイツの下院である連邦議会は22日、1つの経営体(企業)ないし経営体内の各職業グループには1つの労使協定のみが適用されることを定めた単一労使協定法案を可決した。同じ企業内で同一の仕事をしているにもかかわらず、所属する組合が異なると賃金や労働時間に違いが生じるという不平等の回避が狙い。同法案は今後、州政府の代表で構成される連邦参議院(上院)で審議・採決されるものの、同院には拒否権がないため、同院が両院協議会に持ち込まず今後の手続きが順調に進めば7月に施行される見通しだ。
単一労使協定の原則は戦後ドイツの安定的な労使関係の要とされてきた司法判断に基づくルールで、これにより小規模労組の乱立とストライキの多発が抑止されてきた。小規模な労組を設立しても独自の労使協定を締結できず、メリットがなかったためだ。だが、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は2010年、単一労使協定は結社の自由を保障する基本法(憲法)9条1項の規定に抵触するとして、同ルールの無効を言い渡した。
これを受けて同一企業の同一職業グループ内に複数の労使協定が併存するケースが発生するようになった。鉄道機関士労組GDLが昨年以降、ドイツ鉄道(DB)でストライキを執拗に行うのはこの判決が支えとなっているためだ。GDL加入の乗務員のみを対象とする労使協定の締結を経営陣に迫っている。
だが、所属組合が異なるというだけで待遇に違いが生じると従業員間に不平が高まり、企業内の雰囲気が悪化しやすくなる。GDLのDBストが市民生活や経済活動に大きなしわ寄せをもたらしていることもあり、政府は単一労使協定原則の法制化に乗り出した。
同法案の柱は、1つの企業内に複数の労組が存在し労使協定も競合する場合、過半数の従業員が加入する組合が締結した協定を全体に適用するというもので、アンドレア・ナーレス労働相は「少数派労組の消滅を狙ったものではなく」、結社の自由、スト権も侵害しないと強調している。
だが、最終的には多数派労組の協定しか適用されないようになるため、労使協定締結に向けて少数派労組が行うストは「相当性の原則(目的を達成するためにはそれに見合った妥当な手段を用いなければならないという原則)」に抵触。裁判所がストを認めなくなる可能性がある。ストを行っても経営サイドへの要求を貫徹できないのであれば、ストは経済や市民生活に悪影響をもたらすだけで益がないということになる。
スト権が実質的に掘り崩されると、新たな組合員の獲得が難しくなり労組は存続の危機に直面する恐れがあるため、GDLなどは違憲訴訟を起こす意向だ。
ドイツは「スト小国」
今回の法案に対しては、労組が社会に甚大な影響を及ぼすストを十分に抑制できないとの批判もある。例えばルフトハンザ航空を対象に断続的にストを行ってきたパイロット労組コックピットは、パイロットの独占的な労組に当たり、同法案が施行されてもこれまで同様、長期のストを行える。
自治体系保育園を対象に現在、無期限ストを全国展開している統一サービス労組Verdiは組合員数が200万人を超え、多くの分野で多数派労組となっている。同ストでシングルマザーや子持ちの共稼ぎ夫婦が受けるしわ寄せは極めて大きいが、同法案はこうしたストにも効果がない。
このため雇用者団体は交通・公共部門では過度のストを抑制するルールの導入を求めている。
鉄道、航空、保育所といった市民生活に直結する分野で大きなストが相次いで起きていることから、ドイツはストが多いと感じる市民が増えている。だが、国際的にみるとストは比較的少ない。労組系経済研究所WSIのデータによると、ストによって失われた労働日数は被用者1,000人当たり延べ16日(2005~13年の平均)で、フランスの139日、デンマークの135日を大幅に下回る。最も少ないのはスイス(1日)で、これにオーストリア(2日)、スウェーデン、ポーランド(ともに5日)が続く。