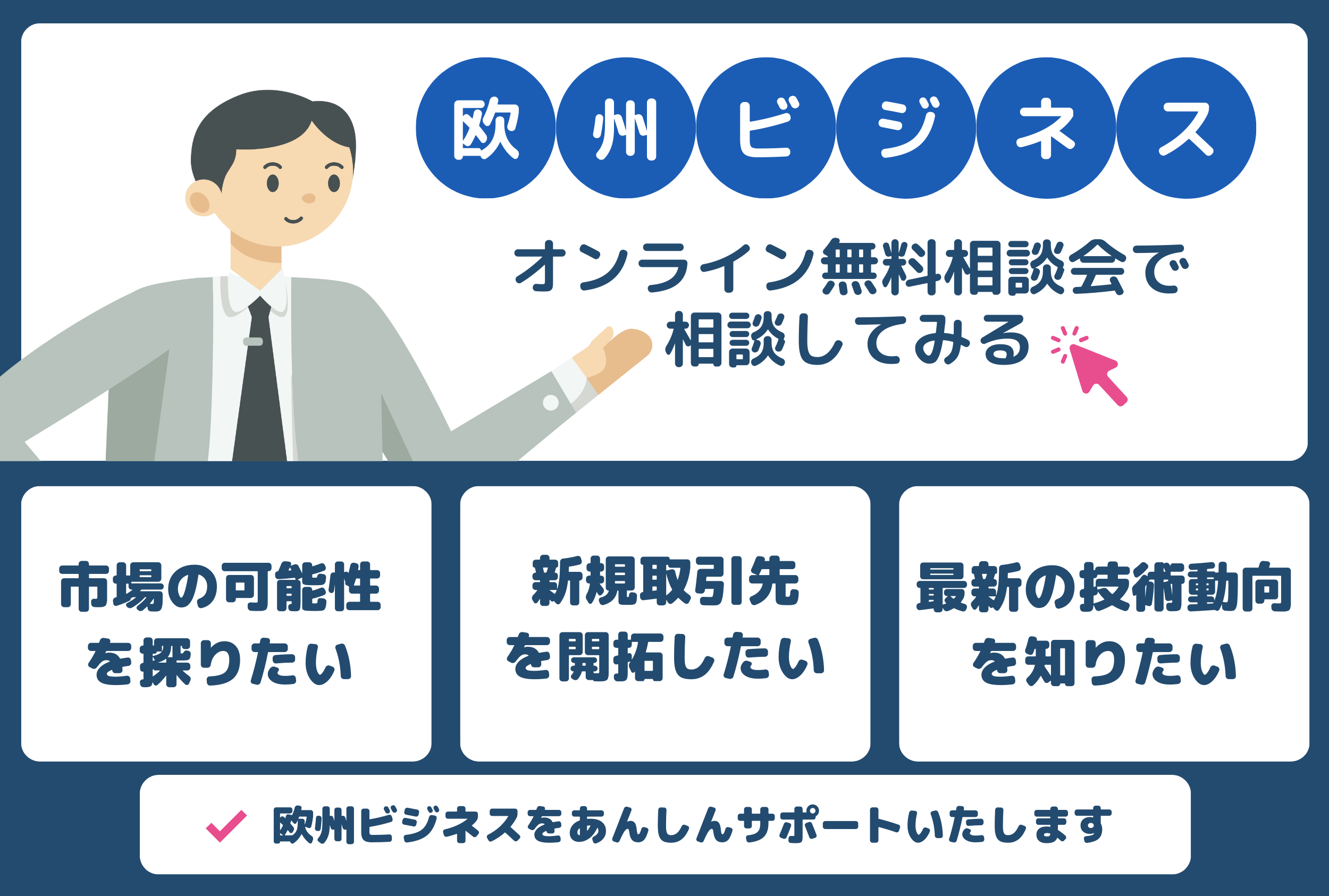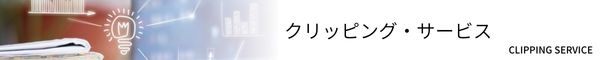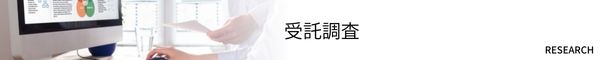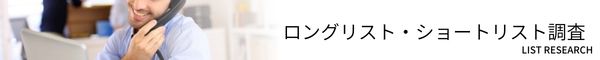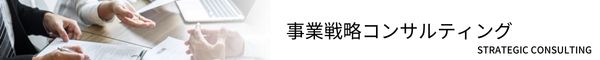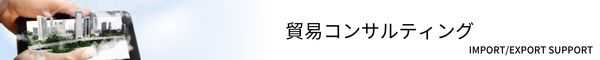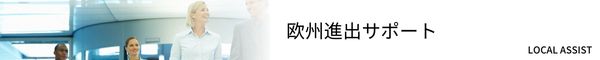フランスのマクロン大統領は4月24日、反政府デモ運動「黄色いベスト」を踏まえた政策方針を発表する記者会見のなかで、ドイツの経済成長モデルを批判した。ドイツの構造改革を手本としてきた従来の姿勢を大きく修正するもので、注目を集めている。両国の間には欧州連合(EU)やユーロ圏のあり方、外交政策をめぐってすきま風が吹いており、今回の大統領発言は独仏の齟齬を改めて印象付けた格好だ。
ドイツでは2000年代前半、中道左派のシュレーダー政権が構造改革「アゲンダ2010」を実施した。手厚い失業保険などにメスを入れるとともに、企業の税・社会保険料負担を軽減することが柱。その効果で「欧州の病人」と呼ばれていた経済は06年から力強く回復した。08年のリーマンショックに端を発する世界的な金融・経済危機からも同国はいち早く立ち直っており、アゲンダ2010は経済低迷に苦しむ他の先進国に“魔法の呪文”のように映った。
フランスも例外でなく、サルコジ大統領(07~12年)とオランド大統領(12~17年)はともに構造改革を目指した。だが、改革は痛みを伴うことから、多くの国民が反発。所期の目的を達成できなかった。
マクロン大統領も17年の就任後、法人税改革や年金改革を通して経済を活性化させる方針を打ち出した。企業の競争力を強化しないことにはフランス経済の地盤沈下に歯止めをかけられないと判断したためだ。
だが、生活が苦しい、あるいは将来に不安を持つ国民はこうした“企業寄り”の路線に失望。燃料価格の上昇をきっかけに黄色いベストのデモ活動が18年5月に始まると、新鮮なイメージを売りにしていたマクロン大統領は強い批判を浴びるようになった。
これに危機感を持った大統領は国民と直接対話して生の声を聞き取る「国民大討論」を1月から3月にかけて全国で実施した。
今回の記者会見はこれを踏まえて行ったもので、50億ユーロ規模の所得減税や公務員削減規模の縮小といった政策方針を打ち出した。減税の財源は企業の税優遇廃止などを通して確保するとしている。
大統領が構造改革路線を修正したこと自体に驚きはない。黄色いベスト運動の参加者を超え、幅広い国民が批判する政策を強行するのはリスクが高いからだ。
だが、ドイツの構造改革を名指しで批判することを予想していた人は少ないだろう。構造改革との決別を明確に示すことで内政上の効果は期待できるものの、EUをけん引するパートナーであるドイツにあえて“ケチをつける”ことに外交上のメリットはない。
欧州の賃金格差は縮小
大統領は記者会見で「ユーロ圏内の不均衡から大きな利益を享受するというドイツの成長モデルは疑いの余地なく終焉を迎えている」と述べた。ドイツ経済はEU域内の低賃金国を利用した生産モデルを通して不均衡を増長してきたとの見方だ。これは、第三諸国の低開発は先進国による収奪によって構造化されたものだとする、1960~70年代にかけて流行した「従属理論」を欧州に当てはめたものと言える。
従属理論は後進国も先進国と同様に近代化するとした単線的で楽観的な発展論(近代化論)を批判し、先進国の経済発展と後進国の低開発が表裏一体の関係にあることを明らかにした点で功績があるものの、1980年代以降、影響力を失った。アジア諸国の経済発展を受けて、低開発からの脱却が可能であることが明らかになったためである。
欧州についてもこれと同じことが言える。EU加盟国の賃金動向をみると、ドイツは17年時点で1時間当たり平均34.1ユーロ、ハンガリーは11.3ユーロだった。その差は約3倍に上るものの、ハンガリーがEUに加盟した04年時点では5倍を超えており、格差は大幅に狭まっている。これはハンガリー以外の新規加盟国にも当てはまることで、ドイツが格差を助長したという批判は当たらない。