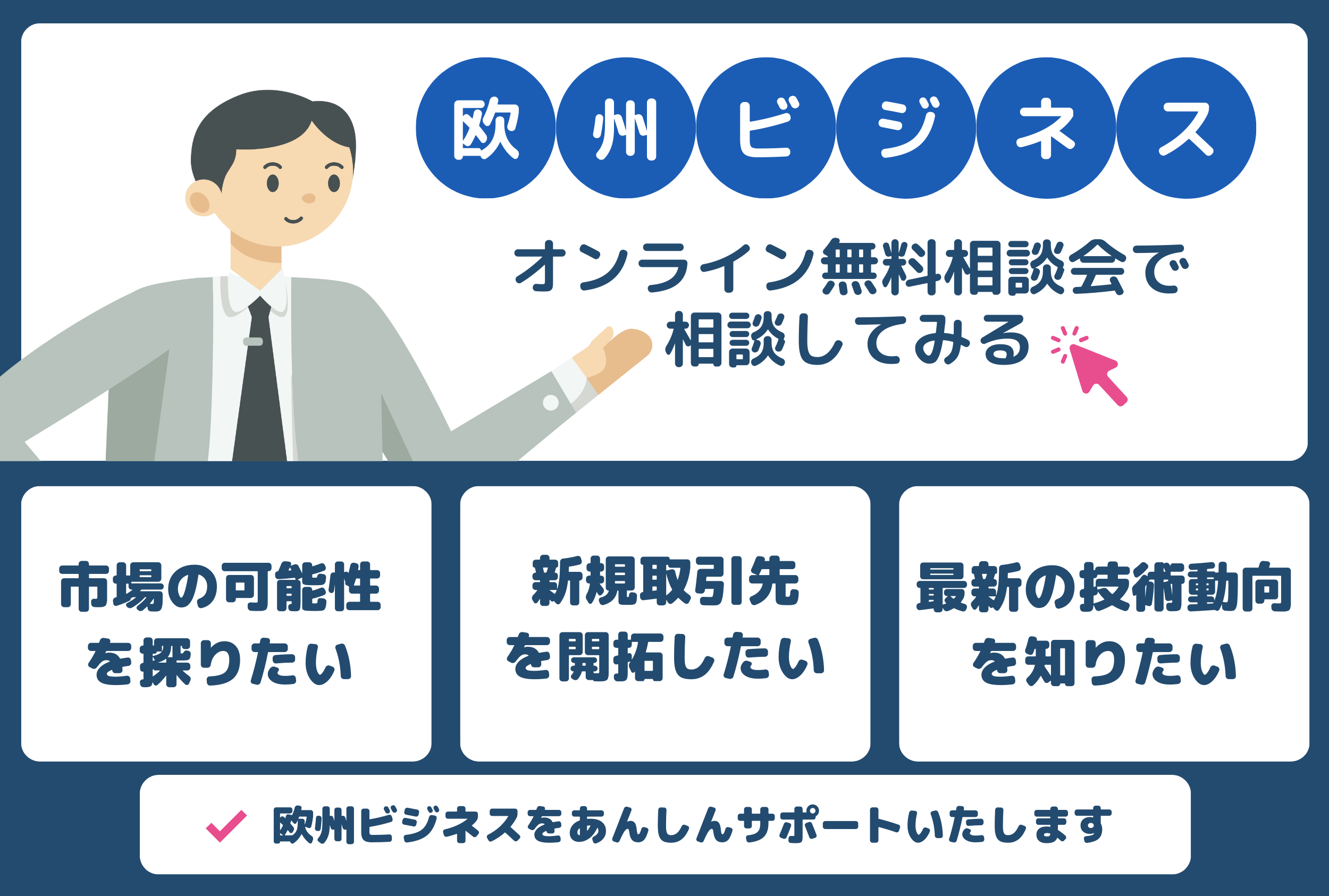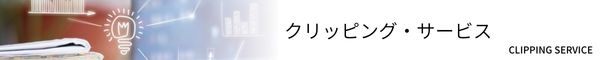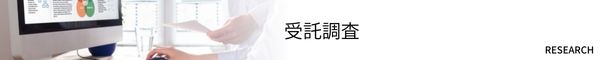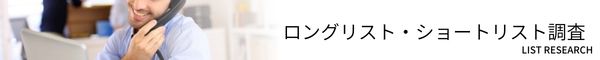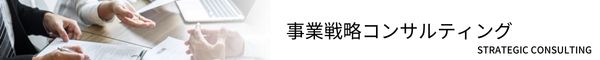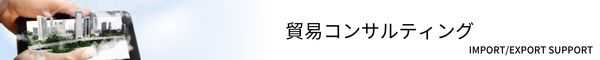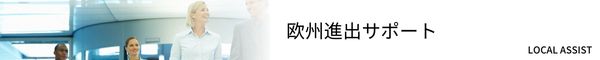ドイツのアンゲラ・メルケル首相と国内16州の首相は6日の電話会議で、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため実施している制限措置を一段と緩和することを決議した。緩和決議は3度目。今回は緩和措置を各州が自らの責任で実施することも取り決めており、すべての州が足並みをそろえるというこれまでの路線は放棄された格好だ。ただ、制限措置が緩和されると感染者が増加する恐れがあることから、新規感染者数が一定水準を超えた地域では制限措置を再強化するというルールが盛り込まれている。メルケル首相は緩和を進めるだけでなく、感染者増に速やかに対応するメカニズムを作り上げることで局地的な感染の拡大が全国に広がることを防止できると指摘。今回の取り決めを「バランスの取れた決議だ」と評価した。
ドイツでは感染者数の急増を受けて、外出や接触、営業を制限する措置が3月中旬に導入された。これらの措置の権限は各州が持っているため、州ごとにルールが微妙に異なっていたものの、当初は足並みがそろっていた。感染者数が医療システムのキャパシティを超えて増える結果、すべての重症・重篤患者に対し例外なく適切な治療をほどこすことができなくなり、「医療崩壊」を招くことへの危機感が強く、制限措置に疑問を挟む余地はほとんどなかった。
だが、4月15日の電話会議で緩和の第一弾が決議されると、足並みに乱れが出てきた。新規の患者数が大幅に減るなかで、企業や市民に大きな犠牲を強い続けることは難しいためだ。州政府は市民やローカル企業の身近な声に特に敏感であることから、国との共同決議から逸脱する緩和を実施する動きが徐々に増加。今回の決議の前には、本来は逸脱に当たる売り場面積規制の撤廃に踏み切ったり、宿泊・飲食業界の営業再開を予告する動きが出てきた。新規感染者数はこのところ毎日、1,000人程度で推移しており、ピーク時の7,000人を大幅に下回っている。
感染者が再び急増することを強く警戒するメルケル首相は州が競うように緩和を進めることに危機感を示してきたが、緩和を禁じる権限を国(連邦)は持たないことから、各州が緩和措置を自ら決定・実施することを認めざるを得なくなった。
飲食店などの営業解禁
今回の決議では◇飲食店、バー、ディスコなどの営業解禁◇ホテルや貸別荘への観光客の宿泊解禁◇フィットネスクラブ、コスメティックサロン、マッサージサロンなどの解禁◇劇場やコンサートホール、映画館の解禁◇遊園地の解禁――などを州が決定する事柄と明記している。
小売店の営業につては売り場面積の大小に関係なく全国で認めることにした。従来の決議では自動車販売店や書店を除いて800平方メートルを超える小売店の営業が認められていなかった。売り場面積当たりの店員と入店者の総数には上限が設けられる。
プロサッカーリーグ「ブンデスリーガ」も無観客を条件に試合を認めることにした。16日から再開される。集客力の高い大型イベントは爆発的な感染拡大の原因となる恐れが高いことから、少なくとも8月末まで禁止される。
国と州はさらに、接触制限措置の緩和を決めた。これまでは家族以外の2人以上と公共の場で集まることを禁止してきたが、今後は2家族が集まることを認める。家族数に関係なく6人以上が集まることを認めたザクセン・アンハルト州のルールはこの決議に合致していないものの、すでに4日付で施行されていることから例外的に容認されている。
住民10万人当たりの感染者数が7日間で計50人を超えた郡と特別市(主に大都市と中都市)では制限措置が再び強化される。これにより感染拡大が他の地域や州、全国に広がるのを防止する。制限強化措置は各州が自らの責任で実施。7日間の感染者数が少なくとも7日連続で50人以下となるまで継続される。
家族以外の人との距離を最低1.5メートル以上に保つ「社会的距離」ルールなどの接触制限は少なくとも6月5日まで継続される。企業に対しては在宅勤務が可能な場合は今後も認めるよう要請している。